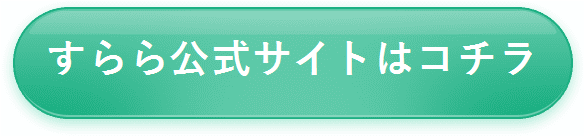すららは不登校でも出席扱いになる?なぜ?出席扱いになる理由について
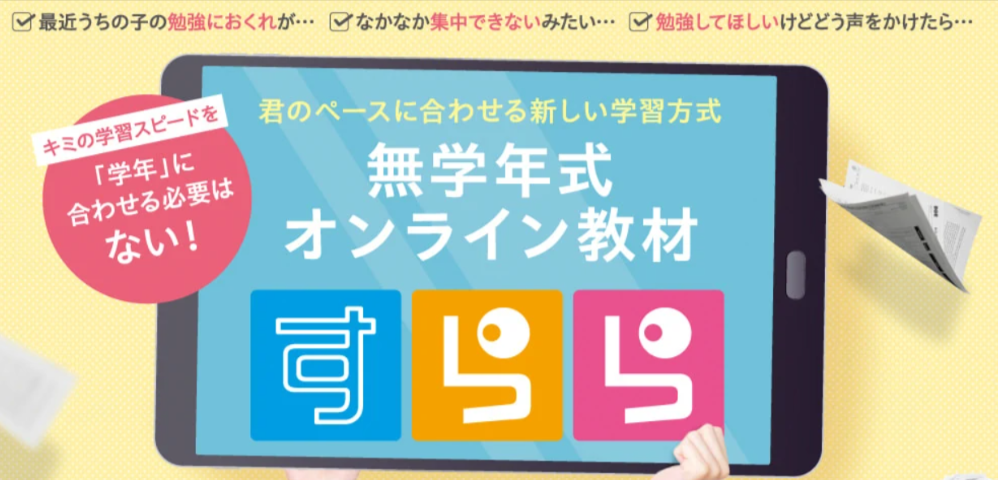
不登校の子どもにとって「出席扱いになるかどうか」は、進級・進学に大きく関わる大切な問題です。
すららは、文部科学省のガイドラインに準拠し、条件を満たせば出席扱いとして認められる家庭用タブレット教材です。
これまでにも、全国の学校で出席扱いが認定された実績があり、保護者や学校の先生からも信頼されています。
本記事では、なぜすららが出席扱いとして認められやすいのか、その理由を5つの観点から詳しくご紹介します。
理由1・学習の質と記録の証明がしっかりしている
すららの大きな特徴は、「学習内容」「時間」「理解度」などの詳細なデータを自動で記録し、学校へ提出可能な学習レポートとして出力できる点です。
これにより、家庭での学習がどれだけ実施されていたかを客観的に示すことができ、学校側も出席扱いにしやすくなります。
さらに、保護者が記録を手作業で管理する必要もないため、無理なく学習履歴を整えることができます。
学校側に「客観的な学習記録レポート」を提出できる
学習した単元や時間、正答率などが詳細に記録され、自動生成されるレポートで学校への提出がスムーズに行えます。
これにより、教師や校長先生が“学習の証拠”として認めやすくなるため、出席扱いの認定に大きく貢献します。
保護者の手間なく、自動的に学習状況が可視化される/これが学校側からも「安心材料」として評価されやすい
保護者が毎回記録をつける必要はなく、すららのシステムが自動で進捗を記録してくれます。
この見える化があることで、担任の先生も安心して「出席扱い」にできるケースが増えています。
理由2・個別最適な学習計画と継続支援がある
すららには、学習を一人で続けるのが難しい子どもでも、無理なく継続できるよう「すららコーチ」がつきます。
このコーチは、子どもの状況に応じて学習計画を立て、定期的に見直しながら進捗をサポート。
さらに、学習の遅れがあっても学年に縛られず取り組める“無学年式”を採用しているため、自分に合ったペースで進められます。
こうした「計画的な学習」「継続的な取り組み」は、出席扱いの条件にマッチしやすい特徴のひとつです。
すららはコーチがいることで、学習の「計画性」と「継続性」をセットでアピールできる
学習の進め方が個人任せではなく、専門スタッフが計画・サポートすることで、「計画的に学んでいる証明」になり、学校にも信頼されやすくなります。
すららは、専任コーチが継続的にサポートし、学習計画を作成してくれる
コーチは月単位での学習計画を立て、進捗が遅れていれば調整をしてくれるので、継続が難しいと感じる家庭にも心強い存在です。
すららは、無学年式で学習の遅れや進み具合に柔軟に対応してくれる
「戻って学ぶ」「先に進む」が自由にできるため、理解度に応じた学びができ、途中からのスタートでも出席扱いを目指せます。
理由3・家庭・学校・すらら三者で連携ができる
出席扱いを申請する際には、学校と家庭、教材提供会社の3者の連携が求められます。
すららでは、必要書類やレポートの準備について、コーチやサポート窓口が丁寧にフォローしてくれます。
また、担任や校長先生への説明が必要な場合も、すららが用意するテンプレート資料などを使ってスムーズに進められます。
家庭だけでは不安な部分を補ってくれる体制があるからこそ、出席扱いの実現率が高くなるのです。
すららは、必要書類の準備方法の案内をしてくれる
「何をどう準備すればいいのか分からない…」という保護者にも、手順を丁寧に解説。
申請に必要な内容をわかりやすく案内してくれます。
すららは、専任コーチが学習レポート(フォーマットの用意)の提出フォローしてくれる
フォーマット付きのレポートは、学校への提出用としてそのまま使える形式。
コーチが書き方までフォローしてくれるから安心です。
すららは、担任・校長と連絡をとりやすくするためのサポートをしてくれる
学校とのやりとりに不安がある家庭でも、すららのサポート体制があれば、スムーズに出席扱い申請を進めることができます。
理由4・文部科学省が認めた「不登校対応教材」としての実績
すららは、文部科学省が示す「出席扱いの要件」に沿った設計がされており、全国の学校・教育委員会と連携して不登校支援を行っている実績があります。
すでに多くの子どもたちが、すららで学習することで出席扱いを受けており、その実例があるからこそ学校側も安心して認めやすいのです。
公的にも実績があり、教育現場での信頼度も高い教材として知られています。
すららは、全国の教育委員会・学校との連携実績がある
文部科学省のモデルケースとして取り上げられた事例もあり、多くの学校で導入実績があります。
すららは、公式に「不登校支援教材」として利用されている
自治体の支援制度と併用されている例もあり、「出席扱いの申請にすららを選ぶ」ご家庭が年々増えています。
理由5・学習環境が「学校に準ずる」と認められやすい
出席扱いの可否を決めるうえで、「その学習環境が学校の教育内容と同等か」という点が重視されます。
すららは、文部科学省の学習指導要領に準拠したカリキュラムを使用し、主要教科のすべてを網羅。
さらに、進捗管理やフィードバック機能もあり、評価の体制も整っています。
こうした点が“学校に準じた教育活動”と判断されやすく、出席扱いに必要な条件を自然と満たしているのです。
すららは、学習内容が学校の学習指導要領に沿っている
国・数・英・理・社すべての主要教科をカバーしており、内容の質も高く、授業の代替として評価されやすい教材です。
すららは、学習の評価とフィードバックがシステムとしてある
学習の理解度や進捗がグラフなどで可視化され、保護者や教師も確認しやすいため、学習活動の証明として非常に有効です。
すららは、専任コーチが学習レポート(フォーマットの用意)の提出フォローしてくれる
すららでは、出席扱い申請時に提出する「学習レポート」のフォーマットが用意されており、それを使って誰でも簡単に必要な情報をまとめることができます。
さらに、専任のすららコーチがフォーマットの記入方法や、どの時点のデータを出力すればいいのかなど、具体的なアドバイスをしてくれます。
申請に慣れていないご家庭でも安心して取り組めるよう、事前準備から提出までの流れを一緒に確認しながら進めてくれるため、申請書類の不備で学校側から差し戻されるような心配も少なくなります。
すららは、担任・校長と連絡をとりやすくするためのサポートをしてくれる
出席扱いに必要なのは、学校との信頼関係とスムーズな情報共有です。
すららでは、担任や校長先生とのやり取りが円滑になるよう、提出レポートの体裁や伝え方のアドバイスまでしてくれます。
「どう説明すれば理解してもらえるか」「どのような書き方が納得してもらいやすいか」など、保護者では判断が難しいポイントも丁寧にフォロー。
とくに初めて申請する場合には、学校とのやりとりで戸惑うことが多いですが、すららが“橋渡し役”となってくれることで、安心して申請を進めることができます。
理由4・文部科学省が認めた「不登校対応教材」としての実績
すららは単なる家庭学習教材ではなく、文部科学省が示す「出席扱いの要件」を満たす教育ツールとして、公式に認められた実績があります。
すでに全国の教育委員会や学校で導入されており、不登校支援の手段として活用されている事例も数多く報告されています。
実績があるということは、それだけ学校側からの信頼も得られているという証。
申請の際も「すららを使っている」というだけで話が通じやすく、スムーズに手続きが進むケースも少なくありません。
すららは、全国の教育委員会・学校との連携実績がある
すららは全国の自治体や教育委員会と連携して、不登校児童への支援を積極的に行ってきました。
導入校は年々増加しており、出席扱いのためのサポート実績も豊富。
自治体によっては、すららの導入が「不登校支援の推奨教材」として明記されている例もあるほどです。
こうした行政との連携があることは、保護者にとっても学校にとっても「安心して使える」証になります。
すららは、公式に「不登校支援教材」として利用されている
すららは文部科学省のガイドラインに準拠した教材であり、「不登校支援用教材」として明確に位置づけられています。
学習の進捗記録、学習内容の妥当性、サポート体制の充実度など、出席扱いの条件を満たすために必要な要素をすべて備えていることから、すでに多くの学校で導入が進んでいます。
不登校になっても「学びの継続」ができる教材として、学校からも紹介されるケースがあるほど、その信頼度は高まっています。
理由5・学習環境が「学校に準ずる」と認められやすい
出席扱いを受けるためには、「自宅学習の環境が学校に準じたものかどうか」が大きな判断基準になります。
すららは、文部科学省の学習指導要領に準拠した内容で構成されており、主要教科をバランスよくカバーしています。
また、単に学ぶだけでなく、理解度の確認テストや学習の記録保存、フィードバック機能も備わっており、“評価可能な学び”が行える設計になっています。
これにより、学校側にも「これは信頼できる教材だ」と感じてもらいやすく、出席扱いの認定がスムーズに進む大きな要因となっているのです。
すららは、学習内容が学校の学習指導要領に沿っている
すららのカリキュラムは、小学校〜中学校までの教科書に準拠しており、文部科学省の学習指導要領をベースにしています。
そのため、家庭で学んでいても「学校と同じ内容を学んでいる」と評価されやすく、出席扱いの条件に合致しやすいのです。
担任の先生や校長先生に説明する際にも、「この教材は指導要領に沿っています」と伝えることで、理解を得やすくなります。
すららは、学習の評価とフィードバックがシステムとしてある
すららは、単に問題を解いて終わりではありません。
正答率や学習時間、理解度に応じて次のステップを提案してくれるシステムがあり、「フィードバック→改善→成長」の循環が可能です。
このように、学習成果を“見える化”できることは、学校側が出席扱いを判断する上での大きなポイントになります。
自己評価だけでなく、コーチやシステムからの客観的な評価があることで、学習の信頼性が高まるのです。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度の申請方法の流れ紹介
不登校のお子さんが家庭での学習によって出席扱いを受けるためには、文部科学省が定めた一定の手続きを踏む必要があります。
とはいえ、実際にどこに相談すればいいのか、何を準備すればいいのか分かりづらいという声も多いです。
ここでは「すらら」を使った出席扱いの制度を申請するための具体的な流れを4ステップに分けてご紹介します。
家庭・学校・医療・教育委員会、それぞれがどのように関わっていくのか、丁寧に解説していきますので、初めての方でも安心して進めていただけるはずです。
申請方法1・担任・学校に相談する
出席扱い制度の申請を進めるうえで、まず最初にすべきことは「担任の先生や学校に相談する」ことです。
これは義務教育課程において、出席認定を決定するのが「校長先生」であるため、必ず学校との合意が必要となるからです。
家庭だけで進めても、学校が了承しなければ出席扱いにはなりません。
特に初めて申請を行うご家庭は、担任やスクールカウンセラーと一度面談の機会を持ち、子どもの現状や学習環境について丁寧に共有しておくと、その後の申請がスムーズになります。
出席扱いの申請に必要な書類・条件を確認する
学校への相談時には、出席扱い制度の適用に必要な書類や条件を必ず確認しておきましょう。
文部科学省が定めるガイドラインでは、「学習の継続性」「適切な学習支援体制」「学習成果の評価」などが要件に含まれています。
すららを使用している場合、それらを満たす学習記録が出力できるため、学校側と事前に「何を提出すればよいか」「どのタイミングで必要か」を擦り合わせておくと安心です。
申請方法2・医師の診断書・意見書を用意(必要な場合のみ)する
すべてのケースで必要ではありませんが、出席扱いの申請には医師の診断書や意見書の提出を求められる場合があります。
とくに「情緒的な理由による不登校(適応障害・ASD・うつ症状など)」の場合には、医療機関の第三者的な意見が重視されることがあります。
診断書があることで、「学校に通うのが困難である」ことの正当性が明確になり、申請の通過率が上がるという声もあるため、必要に応じて準備しておきましょう。
不登校の理由によっては、診断書が求められるケースもある
例えば、家庭での学習はできているけれど、登校するとパニックを起こす、あるいは不安が強く授業に集中できないなど、精神的な理由が背景にある場合は、学校側も「診断書が必要」と判断することがあります。
必要な書類については、事前に学校に確認しておくことが重要です。
精神科・心療内科・小児科で「不登校の状態」と「学習継続が望ましい旨」を書いてもらう
診断書には、「学校に通学することが困難な状態である」ことだけでなく、「家庭での学習継続が本人の発達や安定にとって望ましい」ことを明記してもらえると、学校側の理解も得やすくなります。
医師に相談する際は、すららの利用状況や学習記録なども見せると、より具体的な内容を書いてもらえる可能性が高まります。
申請方法3・すららの学習記録を学校に提出する
すららを使用している場合、最も重要なのが「学習の記録・成果をどう提示するか」です。
すららでは、学習時間・単元・正答率などが自動で記録されており、保護者用マイページから出力できます。
このレポートを学校側に提出することで、「学習していること」「継続的な取り組みがあること」を客観的に証明することができます。
フォーマットは見やすい設計になっており、提出用に最適化されています。
学習進捗レポートをダウンロードし担任または校長先生に提出
提出する学習レポートは、すららの管理画面から簡単にダウンロード可能です。
どの教科をいつ学んだのか、どこまで進んでいるのかが一目でわかる仕様になっているため、学校側にとっても確認しやすく、出席扱いの判断材料として非常に有効です。
紙に印刷して持参するか、PDFでメール送付などの方法も相談しておきましょう。
出席扱い申請書を学校で作成(保護者がサポート)
学習レポートの提出後は、学校側が出席扱い申請書を作成するケースが一般的ですが、保護者が記入を手伝う必要があることもあります。
お子さんの状況、すららを通じての学習内容、家庭での取り組み姿勢などを一緒に記載し、内容に整合性を持たせるようにしましょう。
学校と情報を共有しながら進めることで、よりスムーズに申請が通りやすくなります。
申請方法4・学校・教育委員会の承認
最終的に出席扱いが認められるかどうかは、学校長の判断に委ねられます。
また、一部の地域では教育委員会の承認も必要となるケースがあります。
ここまでの準備が整っていれば、学校側も判断材料として十分な情報を得ているため、申請が却下されるケースは稀です。
大切なのは、「誠実に、継続的に学習していること」を第三者が判断できる形で示すことです。
学校長の承認で「出席扱い」が決まる
担任との相談を経て、校長先生が「学習の継続性」「記録の信頼性」などを総合的に判断し、出席扱いかどうかを決定します。
申請が認められれば、その期間は「欠席」ではなく「出席」として正式に記録され、内申点や進級への影響も回避できます。
教育委員会に申請が必要な場合は、学校側と連携して行う
自治体によっては、学校長の判断のほかに教育委員会への報告や申請が必要なこともあります。
こうした場合でも、すららの学習記録や診断書などが整っていれば問題なく対応できます。
学校が窓口となって進めるため、保護者は指示に沿って書類を提出するだけで済む場合が多いです。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうメリットについて解説
不登校という状況の中で、子どもが家庭で学び続けていても「出席扱い」にならなければ内申点や進学に影響してしまいます。
ですが、すららを利用することで、出席扱いとして認められる可能性が高まり、それによって得られるメリットも多くあります。
ただ学ぶだけでなく、公式に“登校していた”と同じ評価を得られることは、子どもにとっても保護者にとっても大きな安心感に繋がります。
ここでは、すららを通じて出席扱いを認められた場合に得られる3つの具体的なメリットについて詳しく解説していきます。
メリット1・内申点が下がりにくくなる
出席扱いが認められる最大のメリットのひとつは、内申点への影響を軽減できることです。
日本の学校では、出席日数が内申評価に大きく影響します。
たとえ学力があっても欠席が多いと、どうしても内申点が下がりやすくなってしまいます。
すららを通じて家庭学習の継続性が認められ、出席扱いになると、登校と同じように日数がカウントされ、評価への悪影響が最小限に抑えられます。
特に中学や高校の進学時に、内申点が一定以上ないと希望の学校を選べないということもあるため、出席扱いは非常に大きな意味を持ちます。
出席日数が稼げることで、内申点の評価も悪化しにくい
内申点は単なる成績だけでなく、「出席日数」や「授業態度」といった総合的な観点から評価されます。
すららで出席扱いを得ることで、「欠席扱いの日数」が大幅に減少し、結果的に内申点の維持につながります。
これによって、「勉強はしてるのに評価がつかない」という理不尽さを避けることができます。
中学・高校進学の選択肢が広がる
出席日数が足りないことで、推薦や内申点による加点を受けられなくなるケースは少なくありません。
すららで学習を継続し、出席扱いを得られれば、出願条件を満たせる可能性がぐっと広がります。
進路の幅が狭まらずにすむのは、子どもにとっても大きな安心材料となります。
メリット2・「遅れている」「取り戻せない」という不安が減る
不登校中に多くの子どもが感じるのが、「みんなに置いていかれている」という焦りや不安です。
でもすららを使って学習を継続できていれば、その不安を大きく減らすことができます。
すららは無学年式のカリキュラムを採用しているため、「自分のペースで」「わからないところからやり直す」ことが可能です。
さらにAI診断によって苦手を自動で分析し、効率よく復習できる設計になっています。
こうした環境で学ぶことで、「学校に戻る自信」もつきやすくなります。
すららで継続的に学習することで、授業の遅れを気にしなくていい
学校に通えなくても、すららでコツコツと学習を進めていれば、教科書の範囲をカバーできます。
動画講義・ドリル・確認テストが一体化しているため、内容理解もしっかりサポートされていて、「取り残されてる感覚」が薄れていきます。
学習環境が整うことで子どもの自己肯定感が低下しにくい
学びを続ける環境があることで、「自分は何もできていない」という感覚が減り、子どもの心の安定にもつながります。
日々の達成感や「できた」という実感が、自己肯定感を支えてくれるため、精神的な回復にも良い影響を与えます。
メリット3・親の心の負担が減る
不登校の子どもを抱える親御さんにとって、「うちの子の将来はどうなるんだろう」「進学できるのか」といった不安は常につきまといます。
そんな中で、すららを使って出席扱いが得られることは、精神的な安心感をもたらしてくれます。
また、すららには学習をサポートしてくれるコーチがついているため、「親がすべてを教えなければいけない」というプレッシャーも軽減されます。
学校、家庭、すららが三位一体となって子どもの学習を支える体制があることで、親の孤独感や不安も和らぎます。
学校・家庭・すららコーチで協力体制ができる/1人で不安を抱える必要がない
出席扱いの申請時にも、すららのコーチが学習記録の出力方法をフォローしてくれたり、必要書類の提出手順を教えてくれたりと、実務的なサポートも万全です。
親として「どうしていいかわからない」と感じる場面で、専門的なアドバイスが受けられるのは大きな心の支えになります。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための重要な注意点について解説
すららを利用して出席扱いを申請する場合、「条件さえ満たせば必ず通る」というわけではありません。
実際には、学校や自治体の判断によって可否が分かれることもあり、そのためには保護者や本人の「伝え方」「準備の仕方」次第で結果が変わることもあります。
そこで今回は、すららを使って出席扱いを申請する際に知っておくべき注意点についてご紹介します。
学校との関係づくりや、必要書類の準備、学習の質の確保など、事前にしっかり理解しておくことで、スムーズな申請と承認が期待できます。
注意点1・学校側の理解と協力が必須
出席扱いの可否を最終的に判断するのは、学校長です。
つまり、学校側が「この子はきちんと学んでいる」と納得しない限り、どんなに家庭で努力しても出席扱いにはなりません。
そのためには、担任の先生や教頭先生、校長先生と早い段階で丁寧に話をすることが大切です。
すららが文部科学省のガイドラインに沿って設計された教材であることを説明し、疑問や不安を一つひとつ解消していく姿勢が大事です。
場合によっては、すらら公式の資料や学習レポートを印刷して持参すると、話がスムーズに進むケースも多いです。
「すららは文科省ガイドラインに基づく教材」ということを丁寧に説明する必要がある
すららが出席扱いに対応している教材であることを、学校側が知らない場合もあります。
公式サイトや資料を参考に、「文部科学省の出席扱い要件を満たしていること」「全国の学校で実績があること」をしっかり説明することで、安心してもらえることが多いです。
必要に応じて、すららの資料を一緒に持参する/担任だけではなく教頭や校長にも早めに相談する
担任の先生だけで話が進まない場合は、教頭先生や校長先生とも直接面談を設けておくと安心です。
出席扱いの判断権は校長にあるため、早めに上層部に話を通しておくことで後の手続きがスムーズになります。
注意点2・医師の診断書や意見書が必要な場合がある
不登校の背景に、発達特性や精神的な不調がある場合は、出席扱いの申請時に医師の診断書や意見書が必要になるケースが多いです。
これにより、学校側が「登校が困難な状況である」と客観的に判断できる材料となり、申請が通りやすくなります。
診断書には、「現在の状態」「家庭学習の必要性」「本人の意欲」などを含めてもらうことが望ましいです。
事前に医師に相談し、家庭での学習状況を具体的に伝えておくことで、より前向きな記載をしてもらいやすくなります。
不登校の原因が「体調不良」や「精神的な理由」の場合は医師の診断書・意見書が必要になることが多い
心身の不調が理由で登校ができない場合、第三者である医師の診断が説得力を持ちます。
「家庭での学習が必要かつ有効である」という意見があることで、学校側も納得しやすくなります。
通っている小児科や心療内科で「出席扱いのための診断書が欲しい」と伝える
はじめて診断書をお願いする際は、はっきりと「出席扱いの申請を検討しているので、家庭学習の必要性を書いてほしい」とお願いするのがコツです。
医師が目的を明確に理解していると、記載内容も具体的で適切になります。
医師に「家庭学習の状況」や「意欲」を具体的に説明して、前向きな記載をお願いする
すららでどんな内容を学んでいるか、どれくらいの頻度で取り組んでいるかを伝えることで、医師もその重要性を理解しやすくなります。
学習に対して前向きであることが伝われば、診断書の内容もより前向きになります。
注意点3・ 学習時間・内容が「学校に準ずる水準」であること
出席扱いを得るためには、「家庭学習が学校の授業に準ずる内容・時間である」ことが大前提です。
たとえば市販のドリルを適当にこなしているだけでは、学校側が「教育の質が担保されている」とは見なしません。
すららのように、学習指導要領に基づいたカリキュラムで、かつ進捗が記録される仕組みがある教材であれば、その条件をクリアしやすくなります。
計画的に学習が進められていることを示すことで、学校側の納得感も高まります。
出席扱いにするためには、「単なる自習」ではNG/「学校の授業に準じた学習内容」である必要がある
文部科学省の出席扱いガイドラインでは、「教育的に効果があること」が明記されています。
つまり、教材の質・支援体制・評価方法が整っている必要があります。
すららはこうした要件を満たしているからこそ、安心して使える教材なのです。
学習時間は、学校の授業時間に近い形を意識(目安:1日2〜3時間程度)する
出席扱いにするには、単に「勉強している」というだけでなく、学習時間の面でも「学校と同程度の時間を確保している」ことが求められるケースがあります。
もちろん、実際の学校の授業は1日5〜6時間あるため、すべてを完全に再現する必要はありませんが、少なくとも1日2〜3時間を目安に、継続的に学習をしていることが大切です。
すららであれば、単元ごとに学習時間が可視化されるため、どれだけ学習に取り組んだかを記録として残すことができます。
この時間の記録が、学校に「家庭での学習が十分に行われている」という信頼材料にもなります。
全教科をバランスよく進める(主要教科だけだとNGな場合もある)
出席扱いを認めてもらうには、学習内容が「学校で学ぶ内容と同等」であることも求められます。
そのため、国語・数学・英語など主要3教科だけでなく、理科や社会も含めた「全教科」をバランスよく学習することが推奨されます。
すららでは、3教科・4教科・5教科コースから選ぶことができ、出席扱いの申請を見据えるのであれば、5教科対応のコースを選ぶと安心です。
偏りのない学習をすることで、学校側にも「しっかりと学力の維持が図られている」と納得してもらいやすくなります。
注意点4・学校との定期的なコミュニケーションが必要
すららを使って出席扱いを申請・継続するには、「学校とのこまめな連絡」が非常に重要なポイントとなります。
申請して終わりではなく、認定された後も、学習状況の報告や面談を通じて、定期的にコミュニケーションをとっていく必要があります。
担任の先生やスクールカウンセラーとの信頼関係がしっかり築かれていると、「この子は家庭でもきちんと学んでいる」と安心してもらえるので、継続的に出席扱いを得るための土台になります。
学習記録の提出や、簡単な進捗報告のメールでもよいので、学校とのつながりは絶やさないことが大切です。
出席扱いにするためには、「学校と家庭で学習状況を共有」することが条件になることが多い
文部科学省の指針にもある通り、出席扱いにするためには「学校が学習状況を把握していること」が条件とされています。
つまり、どれだけ家庭で学習していたとしても、それを学校に共有していなければ評価の対象にならないということです。
学校との連携は必須と考え、定期的な報告を習慣にすることが望ましいです。
月に1回は学習レポートを提出(すららでダウンロードできる)すると良い
すららでは、学習記録が自動で記録され、月ごとのレポートとして簡単に出力することができます。
これを月1回程度の頻度で担任や校長に提出することで、家庭学習の継続性と信頼性を証明することができます。
学校側にとっても、視覚的に理解しやすい形式のため、受け取りやすく、好印象を持ってもらえるでしょう。
学校から求められた場合は、家庭訪問や面談にも対応する
学校によっては、実際に家庭での学習環境を確認するため、家庭訪問や面談を求めることがあります。
これは、「学習環境が整っているか」「本人に学習の意欲があるか」などを判断するためのものです。
すららで日々の取り組みを続けていれば、堂々と応じることができるので、必要に応じて前向きに対応しましょう。
担任の先生とは、こまめにメールや電話で進捗共有をすると良い
面談や書類提出だけでなく、日々の学習についても、簡単なメールや電話で担任に共有することで、信頼関係が深まります。
「今日は数学を頑張っていました」「来週は英語に力を入れる予定です」など、短い内容でもOKです。
こうした積み重ねが、出席扱いの継続に大きく影響します。
注意点5・教育委員会への申請が必要な場合もある
出席扱いの判断は基本的に校長先生の裁量で行われますが、地域によっては教育委員会への申請・報告が必要なこともあります。
とくに中学生や高校生の場合や、公立学校での申請では、教育委員会のガイドラインに従う必要があるケースもあります。
このような場合は、学校側と協力しながら、必要な資料を準備し、書類を整えていくことになります。
焦らず段階を踏んで進めていけば問題ありませんが、「地域によってルールが違う」という点は頭に入れておくと良いでしょう。
教育委員会向けの資料準備も、学校と相談しながら進める
教育委員会への提出が求められる場合でも、保護者だけで対応する必要はありません。
学校側が窓口となり、一緒に資料を確認しながら進めてくれます。
すららの学習記録や医師の診断書、家庭での学習環境に関する説明文など、必要なものを揃えるためにも、学校と早めに連携しておくことが成功のカギになります。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための成功ポイントを解説
すららを利用して出席扱いを申請する際、単に学習を継続するだけではなく「伝え方」や「準備の工夫」次第で、申請がスムーズに通るかどうかが大きく左右されます。
特に学校側が出席扱いに慣れていない場合や、制度への理解が浅い場合には、「納得してもらう工夫」がとても大切になります。
ここでは、実際にすららを使って出席扱いが認められたご家庭が実践している、具体的な成功ポイントをご紹介します。
すららの強みを上手に活かして、前向きな関係を築きながら出席扱いを目指しましょう。
ポイント1・学校に「前例」をアピールする
学校側が出席扱いに慎重になる最大の理由は「前例がない」「前例を知らない」という不安です。
だからこそ、他の学校で実際にすららが出席扱いに活用されているという事実を伝えることは非常に効果的です。
すららの公式サイトでは、出席扱いに関する実績や導入事例が紹介されているため、それを印刷して持参すれば、学校側の安心感にもつながります。
とくに校長先生や教頭先生への説明時に活用すると、「ほかの学校でも認められているのか」と好意的に受け取ってもらえるケースが多くなります。
「すららで出席扱いになった他の学校」の事例を学校に紹介すると効果的
全国で多数の学校がすららを活用し、出席扱いの申請が認められています。
こうした前例を示すことで、学校も「うちでもできるかも」と前向きになりやすくなります。
保護者が主体的に情報提供を行う姿勢も、好印象につながります。
すららの公式サイトに実績紹介があるので、それをプリントして持参する
すらら公式サイトには、不登校支援や出席扱いの導入実績が豊富に掲載されています。
中学・高校問わず活用されているので、資料としてプリントしておくと、学校との面談の際に非常に役立ちます。
可能であれば、そのページのURLも一緒に提示すると、先生が後から確認しやすくなります。
ポイント2・「本人のやる気」をアピール
出席扱いを申請する際に、学校側が気にするポイントのひとつが「本人の意欲」です。
どれだけ保護者が頑張っていても、本人に学ぶ意志がなければ、継続的な学習とは見なされにくいのが現実です。
そのため、本人の学習に対する前向きな気持ちを、具体的に伝えることが大切です。
たとえば、「すららで頑張った感想」「次に取り組みたい内容」「将来の目標」などを簡単なメモにして提出したり、面談の場で自分の言葉で話すことができれば、学校側にも良い印象を与えることができます。
本人が書いた学習の感想や目標を提出すると良い
「英語の授業が面白かった」「次は理科を頑張りたい」など、簡単な感想でも構いません。
本人が主体的に取り組んでいることをアピールすることで、出席扱いの申請に対する説得力がぐっと増します。
面談がある場合は、本人も参加して「頑張っている」と伝えると良い
もし面談に参加できる状況であれば、本人が直接先生に話をすることで、信頼性が高まります。
「すららでこの教科が面白い」「家でもがんばってます」などの一言でも、学校側の評価は大きく変わります。
ポイント3・「無理なく、継続可能な学習計画」を立てる
出席扱いで最も大切なのは「継続性」です。
最初の数週間だけ頑張っても、すぐに挫折してしまっては意味がありません。
そのためには、本人のペースに合わせた無理のない学習計画を立てることが必要です。
すららには「すららコーチ」がついており、子どもの特性や生活リズムに合わせて、最適なスケジュールを提案してくれます。
あらかじめ現実的な目標を立てておくことで、無理なく長く続けることができ、その結果として出席扱いが継続的に認められやすくなります。
継続が最重要だから、本人に合わせた計画が必須となる
無理な計画を立てて途中で挫折してしまうと、継続的な学習と認められなくなる可能性もあります。
集中できる時間や得意・不得意を考慮した学習計画を立てることが大切です。
すららコーチに相談して、現実的なスケジュールを一緒に立ててもらう
すららのコーチは、不登校や発達特性に理解のある専門スタッフです。
学習スピードや苦手分野を踏まえて「できる範囲での積み重ね」をベースに計画してくれるので、安心して相談できます。
ポイント4・:「すららコーチ」をフル活用する
出席扱いの申請時には、「学習記録」や「学習成果の証明」が必要になります。
すららの最大の強みのひとつは、こうした申請に必要なサポートをコーチがフルで対応してくれることです。
具体的には、学習進捗のレポート作成や、出席扱いに必要なデータの整理、学校への提出に向けたアドバイスなどを受けることができます。
親がすべてを背負わなくてもよいという安心感も大きく、出席扱いの実現に向けて心強いパートナーになってくれる存在です。
出席扱いのために必要なレポート作成や学習証明はコーチがサポートしてくれる
「何をどのように提出すればよいのか分からない」という保護者の不安に対して、すららコーチは具体的にサポートしてくれます。
学校に提出するレポートのダウンロード方法や、必要なデータの整理方法まで丁寧に教えてくれるため、手続きがスムーズに進みます。
すららは不登校でも出席扱いになる?実際に利用したユーザーや子供の口コミ・評判を紹介します>
不登校のお子さんを持つご家庭でよく耳にするのが「すららを利用すると出席扱いになるの?」という疑問です。
実際には、文部科学省が定める「ICT教材を活用した学習支援」が出席扱いの対象となる場合があり、すららもその条件に当てはまることがあります
。ただし、必ずしも自動的に出席扱いになるわけではなく、学校側と保護者がしっかり連携を取り、校長先生の判断を経ることが必要です。
口コミでは「すららを続けることで担任の先生から出席扱いと認めてもらえた」という声や「不登校中でも学習習慣を維持できたのが良かった」という感想が見られます。一方で「学校によって対応が違うので確認が必要だった」という体験談もありました。
出席扱いになるかどうかは学校次第ですが、すららを使うことで学びを止めずに続けられる点は、多くの家庭にとって安心材料になっているようです。
良い口コミ1・うちの子は中2から不登校になり、内申点が心配でした。でも、すららで学習を続けたことで「出席扱い」にしてもらえました
良い口コミ2・ 学校に行けなくなってから勉強が完全に止まってたけど、すららを始めて「毎日ちょっとずつやればいい」と思えた。時間も自分で決められるし、誰にも急かされないからストレスがない
良い口コミ3・ 不登校になってから、家で何もせずにゲームばかり。イライラして何度も怒ってしまっていましたが、すららを導入してから、1日10分でも学習に取り組むようになって、家庭の雰囲気がかなり良くなりました
良い口コミ4・ 小学校の時から算数が苦手で、それが原因で不登校になったけど、すららはアニメで説明してくれるし、ゆっくり復習できたので、だんだん分かるようになった
良い口コミ5・すららを始めて半年経った頃、子どもが「学校の授業も分かりそう」と言い出しました。完全に無理だと思ってた登校が、部分登校からスタートできました
悪い口コミ1・ 低学年だと、すららを一人で操作するのが難しくて、結局親がつきっきり。タブレットを使った勉強というより、「親子で一緒にやるドリル」みたいになってしまいました
悪い口コミ2・最初は頑張ってたけど、やっぱり「一人でやる」ことに飽きてしまいました。キャラが励ましてくれるのも、最初は嬉しかったけど、そのうち「うざい」と感じてしまった
悪い口コミ3・すららで学習は続けていたものの、学校が「出席扱い」を認めてくれませんでした。教育委員会にも相談しましたが、地域によって判断が違うのが辛かった
悪い口コミ4・続ければ続けるほど料金が積み上がっていくので、経済的にきつくなってきました。他のオンライン教材よりは高めの印象。
悪い口コミ5・勉強にブランクがあったので仕方ないけど、「すららをやってすぐに成績が上がる!」ってわけではなかったです
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?についてのよくある質問と回答
すららを利用している保護者の方から特によく寄せられる質問が「不登校でもすららで学習すれば出席扱いになるのか?」というものです。
結論から言うと、すららを活用した学習が出席扱いになるかどうかは、学校や教育委員会の判断によって異なります。文部科学省の方針としてICT教材の活用は推奨されており、条件を満たせば出席扱いとして認められる可能性がありますが、必ずしも一律で認められるわけではありません。
そのため、出席扱いにしたい場合は、担任の先生や学校に事前に相談しておくことが大切です。実際の口コミを見ると「学校に認めてもらえて安心した」「先生が柔軟に対応してくれた」という声がある一方で「地域によって判断が違い、認められなかった」というケースもあります。
いずれにしても、すららを通じた学習が子どもの学びを止めず、自信の回復や社会復帰の一歩につながる点は大きなメリットだと言えるでしょう。
すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?
「すらら うざい」という口コミは、個々の利用者の体験や期待と教材とのミスマッチによるものが多いようです。
たとえば、親が望むほど子どもが自発的に取り組まないケースや、料金に対する成果が感じにくかったという声が背景にあります。
また、AI教材という新しいスタイルに戸惑いを感じた保護者が投稿するケースもあります。
ただ、すらら自体は継続率・満足度ともに高く、評価している家庭も非常に多いため、「うざい」という声が必ずしも教材の質を表しているわけではありません。
無料体験や体験談の比較で実際の使用感を確認するのが一番の対策です。
関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較
すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください
すららには「発達障害専用コース」といった明確な区分はありませんが、発達特性に配慮した内容やサポートが標準で含まれています。
そのため、発達障害や学習障害がある子でも安心して利用できるユニバーサルデザイン設計となっており、料金も一般のコースと同一です。
サポート面では、すららコーチが子どもの特性や学習状況に応じた進め方を提案し、継続的な支援をしてくれます。
また、学習時間を可視化し、苦手分野をAIが自動分析してくれる機能も標準搭載されています。
料金に障害者割引制度などはないものの、内容面での手厚さを考えると十分納得できる内容です。
関連ページ:すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?
すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?
はい、すららは文部科学省が定める「出席扱い要件」に対応した教材のひとつで、多くの学校や教育委員会で出席扱いとして認められています。
ただし、学校長の判断が最終的な決定権を持つため、すららでの学習を出席扱いにしたい場合は、学校との連携が必要です。
すららでは、学習の進捗や時間、理解度を自動記録し、レポートとして提出できる機能があります。
また、専任のコーチが出席扱いに必要な学習証明のサポートも行ってくれるため、不登校の子でも安心して学習を続けることが可能です。
関連ページ:すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて
すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください
すららでは、入会時にキャンペーンコードを入力することで、入会金無料や割引特典を受けることができます。
キャンペーンコードは公式サイトや提携ブログなどで発行されており、期間限定のものも多いので注意が必要です。
入会申し込みフォームの所定の欄にコードを入力するだけで特典が適用されますが、入力忘れやタイミングによっては無効になる場合もあるため、申込前にしっかり確認しておくことが大切です。
うっかり入力を忘れてしまった場合でも、申し込み直後であればカスタマーサポートに相談すれば対応してもらえることもあります。
関連ページ:すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について
すららの退会方法について教えてください
すららの退会には、「解約」と「退会」という2つのステップがあります。
解約は月額利用の停止を意味し、退会は会員情報の削除を指します。
解約は必ず電話(すららコール)でのみ受付されており、WEBやメールからの手続きはできません。
解約時には、契約者情報(氏名・登録電話番号・ユーザーID)を伝える必要があります。
解約が完了しても、データは残るので再開もスムーズです。
もし今後の再利用の予定がなければ、解約時に「退会」希望を伝えることで、学習履歴ごとアカウント削除も可能です。
関連ページ:すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?
すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?
すららでは、基本的に入会金と月額受講料のみが必要で、その他の教材費やシステム利用料などは発生しません。
紙のテキストを購入したり、別途機材をレンタルする必要もないため、費用は非常に明瞭です。
自宅にあるパソコンやタブレットで学習を進められるため、端末費用も抑えられます。
ただし、インターネット接続は必要になるため、Wi-Fi環境の整備や通信費などは家庭で負担する必要があります。
追加費用がかかることなく学習をスタートできる点も、すららの魅力のひとつです。
1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?
すららは、1人ひとりの学習履歴や進捗状況、苦手分析が個別に記録・管理される仕組みになっているため、兄弟で1つの契約を共有することはできません。
それぞれの学習レベルに合ったカリキュラムを個別に受けるためにも、1人につき1アカウントが必要です。
ただし、兄弟で同時に入会する場合は、キャンペーンで入会金が割引になることもあります。
また、家族単位での管理がしやすいように、保護者用の管理画面から複数のアカウントを一括確認することも可能です。
すららの小学生コースには英語はありますか?
すららの小学生コースには、英語も標準で含まれており、初歩から中学レベルの文法まで学べる内容になっています。
とくに初めて英語を学ぶお子さまにも配慮された内容で、「聞く・話す・読む・書く」の4技能をバランスよく学べる設計です。
アニメーションキャラが優しくナビゲートしながら進むので、英語に苦手意識がある子でも楽しく取り組める点が好評です。
小学生のうちから英語に親しませたいと考えている保護者にとって、すららの英語コンテンツは安心して任せられる教材と言えるでしょう。
すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?
すららのコーチは、子ども一人ひとりの学習状況に合わせて最適な学習計画を提案し、目標設定やペース調整をサポートしてくれます。
とくに、発達特性がある子や、不登校で学習に不安を感じている子に対しては、「できた」「わかった」を引き出す声かけや、無理のないスケジューリングで学習へのハードルを下げてくれます。
また、保護者に対しても、声かけの仕方やモチベーション維持の方法などについてのアドバイスが受けられます。
コーチとの連携があることで、家庭学習の負担が軽減され、安心して継続できる仕組みが整っています。
参照:よくある質問(すらら公式サイト)
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?他の家庭用タブレット教材との違いを比較しました
不登校支援に力を入れている家庭用タブレット教材は増えてきましたが、「本当に出席扱いになるの?」「どこまで学校に対応してくれるの?」という点で差が出てくるのが現実です。
この記事では、すららをはじめとした代表的な教材について、出席扱いの実績・対応方法・サポート体制を比較しています。
また、すららのコーチ制度や学習レポート機能が、学校との信頼関係づくりにどう役立つのかも詳しく解説。
制度面と実用性を両立したい方に、ぴったりの内容です。
| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |
| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |
| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |
| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |
| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |
| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |
| ヨミサマ。
|
16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |
| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度・注意点・申請手順まとめ
「すららってよく聞くけど、本当に出席扱いになるの?」「学校に認めてもらえるのかな…」と不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
結論から言うと、すららは文科省ガイドラインに準拠しており、学校や教育委員会への対応実績も多数ある、安心して使える教材です。
この記事では、出席扱いになるための制度的な条件や、申請手順、保護者が気をつけたいポイントを丁寧にまとめています。
今すららを検討している方も、すでに利用中の方も、制度をしっかり理解しておくことで、より安心して家庭学習に取り組めます。