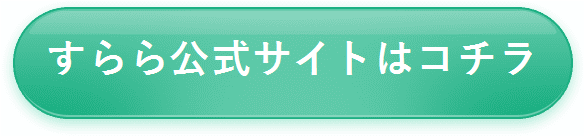すららはうざい!?すららが選ばれるおすすめのポイントを詳しく紹介します
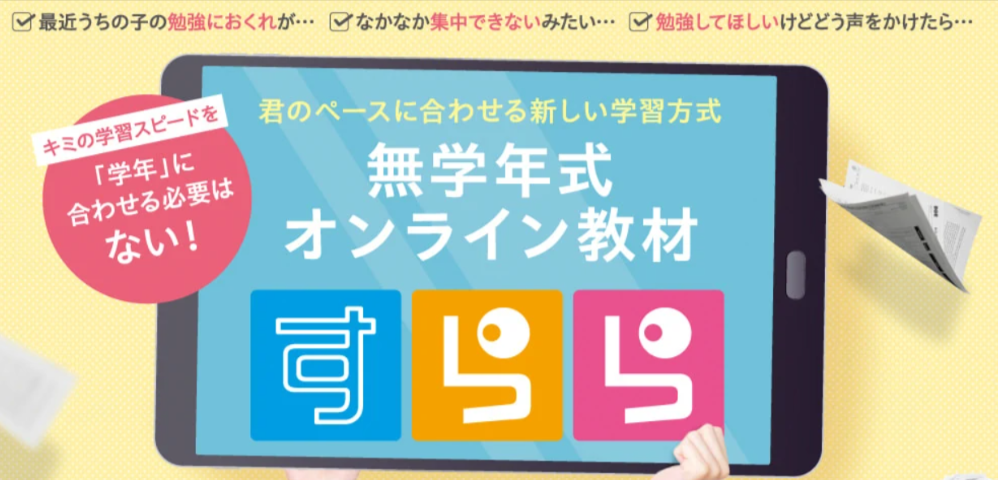
「すららって検索すると“うざい”って出てくるけど、大丈夫?」と気になった保護者の方もいるかもしれません。
ですが実際には、その言葉とは真逆の評価を受けているのが「すらら」です。
無学年式の柔軟な学習スタイルや、アニメーションで進む対話型の授業など、他の教材にはない工夫がたっぷり詰まっています。
飽きやすい子でも集中しやすい仕組みや、わからないところをその場で解決できる設計など、「つまずきゼロ」で続けられるオンライン教材として注目されています。
ここでは、そんなすららが多くのご家庭に選ばれている理由や、おすすめのポイントを詳しくご紹介していきますね。
すららのおすすめポイントをまとめました
| ポイント | 具体例 |
| 無学年式 | 小1の子が中学英語も学べる!苦手もじっくり戻れる |
| 対話型授業 | アニメキャラとの対話形式で「双方向」学習 |
| すららコーチ | 親がスケジュール管理しなくてOK!丸投げ可能 |
| 発達障害・不登校対応 | AIがつまずきを解析→無理なく学習再開できる |
| 成果が見える | テスト・レポート・定着診断で、親も安心 |
| 英語3技能対応 | 話す・聞く・読むがまんべんなく学べる |
| 兄弟OK | 1契約で複数人OK→家族で使えば超コスパがいい |
ポイント1・無学年式!学年に縛られず、得意も苦手も自由に学べる
すららの大きな特徴のひとつが、「無学年式」の学習スタイルです。
学年や年齢にとらわれることなく、今のお子さまの理解度に応じて自由に学べるのが魅力です。
「算数がちょっと苦手だから、2年生の内容に戻って復習したい」「国語は得意だから先に進みたい」など、柔軟に調整できるので、無理なく・ムダなく学びが進められます。
学校ではなかなかできない“個別最適化”が、自宅で実現できるのは嬉しいですよね。
勉強に自信を失ってしまったお子さまにも、「自分のペースでOK」と思える安心感を与えてくれる教材です。
学力や進度に関係なく、自分のペースで学べる
すららは、テストの点数や学年に合わせるのではなく、「今の自分がどこでつまずいているか」「どこまでなら理解できているか」を基準にして学習内容を選べます。
そのため、焦らずじっくり取り組みたい子にも、どんどん先へ進みたい子にもフィットする教材です。
「得意はどんどん進める」「苦手はじっくり戻る」が簡単にできる
すららでは、各単元が細かく分かれていて、どの単元からでも自由にアクセスできます。
だから、「ここはわかってるから飛ばしたい」「この部分はまだ苦手だから復習したい」という学習がスムーズにできるんです。
お子さまのやる気や理解度に合わせた“ぴったり学習”が実現できる仕組みになっています。
ポイント2・「対話型アニメーション授業」で、わかりやすい&飽きない
すららの授業は、ただ映像を見るだけではありません。
キャラクターが先生役となって「会話形式」で授業を進めてくれるのが特徴です。
子どもが質問に答えたり、選択肢を選んだりしながら進んでいくので、受け身の学習になりにくく、集中力が続きやすい工夫がされています。
さらに、難しい内容もアニメーションや図で視覚的に表現されているので、「なるほど!」「そういうことか!」と納得しながら学べるんです。
まるでゲームのように楽しみながら取り組めるので、「勉強イヤだな…」という子にもおすすめです。
アニメキャラが「先生役」として、子どもと会話しながら進めてくれる
授業に登場するキャラクターたちは、まるで家庭教師のように子どもに寄り添いながら進めてくれます。
「それでね、こうなるんだよ」「じゃあ、次の問題はどう思う?」といった対話で進むため、自然と子どもの興味が引き出されます。
勉強というよりも“楽しいやりとり”として受け入れられるのが大きなポイントです。
難しいことも「図や動き」で視覚的に理解できる
文章だけでは理解しにくい内容も、図解やアニメーションで視覚的に説明されるので、イメージで理解しやすくなります。
特に算数や理科など、動きのある説明が必要な単元ではその効果が抜群。
視覚的に「なるほど!」と感じながら進められるので、理解のスピードもグンと上がります。
キャラが褒めてくれるからやる気UP!飽きっぽい子でも続きやすい
すららの対話型授業では、アニメキャラが子どもを励ましたり、正解したときに褒めてくれるのも大きな魅力のひとつです。
「よくできたね!」「その調子!」といった声かけがあることで、お子さまのモチベーションがぐんとアップします。
こうしたポジティブなフィードバックがあることで、「もっとやってみよう」という気持ちが自然と芽生えてくるんですよね。
特に飽きっぽいタイプのお子さまでも、楽しく・前向きに学習を続けやすくなる工夫が詰まっています。
勉強を「やらされてる」ではなく、「やりたいこと」に変えてくれるのが、すららの強さです。
ポイント3・「すららコーチ」がついて親の負担が激減
すららでは、ただ教材を渡して終わりではなく、「すららコーチ」と呼ばれる専門のサポーターが学習全体をサポートしてくれます。
お子さまの学習状況や性格、得意・不得意を見ながら、一人ひとりに合った学習計画を立ててくれるので、親が手間をかけてスケジュールを組んだり、「今日やったの?」と毎日声をかける必要もありません。
継続のコツややる気の引き出し方まで丁寧にアドバイスしてくれるので、保護者の負担をグッと軽減しつつ、お子さまの自立学習も応援してくれます。
まさに「見守るだけ」でOKの安心サポート体制です。
プロの「すららコーチ」が学習計画を作成&フォローしてくれる
すららに登録すると、学習サポートのプロである「すららコーチ」が付き、お子さまの目標や生活リズムに合わせた学習計画を立ててくれます。
「どこから始めたらいいかわからない」「続くか心配…」という方でも、無理のないスケジュールで安心してスタートできます。
子どもの特性や希望に合わせたオーダーメイド学習計画を立ててくれる
すららの強みは、「この子にはこの方法が合うかも」という細やかな配慮が行き届いていること。
やる気を引き出すタイミングや、スモールステップでの計画など、お子さま一人ひとりに合った方法でサポートしてくれます。
画一的な指導ではないのが、継続率の高さにもつながっています。
質問や相談はコーチに直接できるから親は見守るだけでOK
わからない問題があったときや、学習のモチベーションが下がったときには、コーチに直接相談ができる仕組みがあります。
「うちの子に合った進め方は?」「最近やる気がなくて…」といった親からの相談もOK。
親子だけで悩まずに、第三者のサポートが受けられるのは心強いですよね。
ポイント4・発達障害・不登校にも対応!学習への不安を取り除いてくれる
すららは、一般的な学習教材とは異なり、発達障害や不登校といった個別の事情にも対応できる柔軟さがあります。
実際に、文部科学大臣賞を受賞しており、学習支援の観点からも非常に高く評価されている教材です。
学校に通っていない期間があっても、「今の自分に必要な学び」に戻って取り組めるので、無理なく、安心してスタートできるのが魅力です。
また、「勉強が苦手」「つまずきが多い」というお子さまにも、キャラとの対話やステップアップ式の授業で、少しずつ“わかる”を積み重ねていくことができます。
文部科学大臣賞も受賞している学習支援ツール
すららは、ただのタブレット教材ではなく、社会的にも認められた学習支援ツールです。
文部科学省からの表彰を受けていることからも、その教育的価値の高さがうかがえます。
信頼できる教材を選びたいというご家庭にとっては、大きな安心材料になりますね。
発達障害(ADHD、学習障害など)の子にも適した設計で安心
集中が続きにくい、読み書きに困難があるなど、学習に特性のあるお子さまにも配慮された設計になっているのが、すららの大きな魅力です。
アニメーションでの説明や、対話形式の授業、スモールステップの学習進行など、無理なく・楽しく学べる工夫がたくさん詰まっています。
不登校で学校の授業に追いつけない子でも取り組みやすい
すららは、「しばらく学校に行けていなかった」「授業が止まっていて不安」というお子さまにも安心して使える教材です。
無学年式だから、学年に関係なく“今の自分”に合ったレベルからスタートできるんです。
学校のように「今ここをやらなきゃいけない」という縛りがないので、つまずいてしまった単元をゆっくり復習したり、調子の良い日は先に進んだりと、自由度の高い学習ができます。
「もう無理かも…」と感じていた子でも、自信を取り戻せるきっかけになる教材ですよ。
つまづきをAIが解析→理解不足の箇所を自動で出題してくれる
すららには、AIが学習履歴をもとに「どこでつまずいているのか」「何が理解できていないのか」を解析してくれる機能があります。
その結果に応じて、理解不足の部分にピンポイントで戻ったり、補強問題を自動で出題してくれる仕組みになっているので、効率よく苦手を克服することができます。
子ども自身が「ここがわからない」と言い出さなくても、AIがそっと気づいてくれる安心感があるんです。
ポイント5・オンラインテスト&リアルタイム学力分析で、成果が見える
すららでは、学習の成果を“見える化”してくれるオンラインテスト機能も充実しています。
単元ごとに小テストがあり、その結果をもとにすぐに復習したり、対策問題に取り組めるようになっているので、「ただやって終わり」ではなく、ちゃんと理解を深めながら進められるのがポイントです。
また、学習履歴や定着度はすべてAIが分析してくれるので、苦手な分野をすぐに把握・対応できます。
保護者にもレポートが配信されるので、「うちの子、どこまでわかってるの?」という不安もなく、安心して見守れますよ。
小テストで間違えた問題を即フィードバックできる
学習の後には、その単元に関連する小テストが用意されています。
間違えた問題はすぐにフィードバックが表示され、どこでつまずいたのかを視覚的に確認できるので、記憶が新しいうちに復習できるのが魅力です。
こうしたサイクルが自然に組み込まれているので、無理なく学習の定着が図れます。
定着度診断でAIがどこが苦手か把握し即対策問題を出してくれる
AIによる定着度診断では、子どもの解答傾向をもとに苦手分野を自動で判定。
必要な部分だけを集中して学べるので、効率よく“わからない”をつぶしていけます。
漫然と復習するのではなく、狙いを絞って取り組めるのは、やる気の維持にもつながります。
保護者にもレポート配信し「何をどこまで理解しているのか」をしっかり確認できる
すららでは、子どもの学習状況をまとめたレポートが定期的に保護者に送られてきます。
「今日はどこを勉強したのか」「どこが苦手か」「どれだけ進んだか」などが一目でわかるようになっており、忙しい中でも把握しやすくなっています。
必要以上に干渉せずに済むので、親も子もストレスなく続けられます。
ポイント6・英語が「リスニング」「リーディング」「スピーキング」の3技能対応
すららの英語は、読み書きだけではなく、「聞く」「話す」といったコミュニケーション重視のスキルまでしっかりカバーしています。
ネイティブ音声によるリスニング教材が用意されていて、正しい発音やイントネーションを自然に聞き取る力を養うことができます。
また、スピーキングに関しても音声をまねして発音する練習が組み込まれているので、ただの受け身学習ではなく、自分の口で表現する練習もバランスよく取り入れられます。
中学校以降の英語学習や英検対策にもつながる力がしっかり育つ構成です。
ネイティブ音声のリスニングを学ぶことができる
授業の中で使用されている英語音声は、すべてネイティブスピーカーの発音で構成されています。
スピードやイントネーションも自然なので、「本物の英語の音」に触れる経験ができます。
早いうちから英語耳を育てておくことで、将来的なリスニング力に大きな差が出てくるので、これは大きなポイントです。
音読チェックでスピーキング練習ができる
すららでは、リスニングだけでなくスピーキング練習にも対応していて、音読チェックの機能があります。
ネイティブの発音を聞いたあと、子どもがその音声をまねして話すことで、「話す力」を自然に育てていくことができます。
録音された自分の声を聞き返すこともできるので、「こんなふうに話せるようになった!」と成長を実感しながら取り組めます。
学校の授業ではなかなか練習できないスピーキングを、自宅で手軽にトレーニングできるのはとても大きなメリットです。
単語・文法もアニメーションで丁寧に解説してくれるから英検対策におすすめ
すららの英語講座では、単語や文法の基礎もしっかりアニメーションで説明してくれるので、「なぜこうなるの?」という疑問が自然と解消されます。
特に、英検5級や4級レベルの内容に該当する基礎文法が丁寧にカバーされているので、先取り学習や復習としても非常に役立ちます。
試験のためだけでなく、英語の仕組みそのものが「なるほど」と思えるような説明が多いため、苦手意識がある子にもおすすめです。
英語の基礎をしっかり固めたいご家庭にとって、すららは心強い味方になります。
ポイント7・料金体系が「1人分じゃない!」兄弟OK&科目追加自由
すららの料金体系は、他のオンライン教材とは一線を画しています。
なんと、1つの契約で兄弟姉妹が一緒に使えるんです。
たとえば、小学生の兄と中学生の妹がいるご家庭でも、それぞれが自分に合った学年・教科で学習を進めることができます。
追加料金がかからないため、家庭内での学習コストを大幅に抑えられるのが大きな魅力です。
また、教科ごとに必要なものだけを追加していくことができるので、「英語と算数だけ使いたい」など、自由度の高いカスタマイズが可能です。
無駄なく、効率よく使える仕組みになっているので、兄弟のいるご家庭には特におすすめです。
1つの契約で兄弟同時利用OK!(人数分の追加料金なし)
すららは、1契約につき1端末ではなく、家族単位での利用が可能です。
兄弟姉妹がそれぞれ自分のアカウントでログインし、別々の学年・教科で学習していても、追加料金は一切かかりません。
兄弟のいるご家庭にとっては、かなりコスパの良い学習スタイルですね。
小学生の兄と中学生の妹、同じ契約内で利用できるからコスパがいい
すららは、小学生~高校生まで幅広い学年に対応しているので、たとえば「小5の兄は算数メイン」「中2の妹は英語重視」といった学び方も、1つの契約の中で自由に実現できます。
塾を2人分通わせるより圧倒的に安く、家庭内で無理なく学習環境を整えられるのは嬉しいポイントです。
科目ごとに選んで追加できるから、無駄がない
すららでは、「全部入りの高額プラン」ではなく、必要な科目だけを選んで追加できるシステムになっています。
「算数だけやりたい」「英語と国語を追加したい」など、家計や学習状況に合わせてカスタマイズできるので、無駄な出費を抑えつつ効果的な学習が可能です。
これも保護者から高評価を受けている理由のひとつです。
【すらら】はうざい!?本当?他の家庭用タブレット教材にはないすららのメリットについて解説
「すらら うざい」という検索結果を見かけて、不安になった方もいるかもしれません。
でも実際には、すららは“うざい”どころか、多くの家庭から高く評価されている教材なんです。
特に、他の家庭用タブレット教材にはない「対人サポート」や「不登校・発達障害への対応力」は、すららならではの強みです。
学力だけでなく、子どもの学ぶ姿勢や心の状態にまで寄り添ってくれるのが、他の教材との大きな違いです。
ここでは、そんなすららの本当の魅力を、他社との比較も交えながらご紹介していきますね。
メリット1・対人サポート付き!「すららコーチ」がある
すららの最大の強みのひとつが、「すららコーチ」と呼ばれる専任の学習サポーターがついてくれる点です。
多くの家庭用タブレット教材は「自学自習」が前提ですが、すららでは子どもの学習状況をコーチが常にチェックし、必要に応じて声かけや計画の見直しなども行ってくれます。
特に、自分で計画を立てたりモチベーションを維持するのが難しいお子さまには、この対人サポートがとても効果的なんです。
「今日はどこまでやるの?」「この単元苦手だったね」など、寄り添ったフォローで“ひとりじゃない学習”が実現できるのが、すららならではの安心感です。
すららはプロの学習コーチが進捗を管理してくれる
すららのコーチは、教育の専門知識を持ったスタッフが担当していて、子どもの進捗状況を毎週チェックしながら、必要に応じてサポートしてくれます。
「最近ちょっとペースが落ちてるかな」「次はこの単元を重点的にやろう」といった的確なアドバイスがもらえるので、勉強の継続が苦手なお子さまでも安心して続けられます。
コーチが学習スケジュールを子どもに合わせて作成してくれる
画一的なカリキュラムではなく、すららではお子さまの学年・理解度・生活リズムに合わせた“オーダーメイドの学習スケジュール”を作成してくれます。
「週3回だけ集中して進めたい」「習い事のない曜日にがんばりたい」など、家庭の都合に合わせて柔軟にプランを調整してもらえるのも嬉しいポイントです。
メリット2・不登校・発達障害対応に特化している
すららは、不登校や発達障害を持つお子さまへの支援にも力を入れており、その実績が評価され、文部科学省にも推奨教材として紹介されています。
一般的な教材では対応が難しいケースでも、すららなら「やりたい気持ち」「できた達成感」を引き出す設計がされているんです。
特に、学校に通うのが難しい期間中でも、すららで学習を継続していれば「出席扱い」として認められる学校も多く、学習と学校生活のつながりを保つことができるのは大きなメリットです。
「今の状況に合った学び方をしたい」というご家庭には、心強い選択肢になりますよ。
不登校や発達障害の子向けに、文科省推薦教材として採用されてる実績がある
すららは、文部科学省が推進する「教育支援システム」として実際に多くの自治体や学校で採用されてきた実績があります。
個別のニーズに応じた学習支援ができる点や、継続しやすい学習設計が評価され、特に不登校や学習障害のあるお子さま向けの教材として高い信頼を得ています。
不登校児童に対して「出席扱い」される学校も多い
すららでの学習は、自治体や学校の判断によって「出席扱い」になる場合があります。
これは、学習の記録や進捗がデータで管理されていて、第三者がその内容を確認できるからこそ実現できる仕組みです。
家庭学習をしながら、学校とのつながりも維持したい方には大きな安心材料になりますね。
ASD・ADHD・LD(学習障害)に合わせたカリキュラム&サポートが受けられる
集中力が続きにくいADHDタイプのお子さまや、読み書きに苦手意識のあるLDタイプのお子さまにも配慮された内容になっており、「スモールステップで進む」「図解・音声つきで理解しやすい」などの工夫が随所にちりばめられています。
また、すららコーチとのやり取りも個別に調整できるので、お子さまの特性に寄り添った無理のない学び方が可能です。
メリット3・学年を超えた「無学年学習」ができる
すららは、一般的な教材のように「学年ごとの固定カリキュラム」ではなく、無学年式のスタイルを採用しているのが大きな特長です。
今の学年に関係なく、前の学年に戻ったり、先の学習にチャレンジすることができるため、得意な科目はどんどん進め、苦手な分野はゆっくり復習するなど、個別に合わせた学び方が可能です。
「学校でつまずいたけど、どこに戻ればいいのかわからない…」という子にもぴったりです。
発達に特性があるお子さまでも、自分のペースで無理なく進められるため、「わからないまま置いていかれる不安」がありません。
誰でも“今の自分”から学び直せる柔軟さが、すららの魅力です。
学年関係なく自由にさかのぼり・先取りできる
単元ごとに自由にアクセスできるすららの仕組みなら、1つ前の学年にさかのぼることも、2学年先を先取りすることもOK。
「学年の枠にとらわれない」ことで、今必要な内容に集中できる学びが実現します。
勉強の遅れを感じている子にも、背伸びしてチャレンジしたい子にもおすすめです。
発達障害の子は「つまずいたまま進まない」からマイペースに進められるのはポイント
ASDやADHDなど、学習において特別なサポートが必要な子にとって「自分のペースで進める」ことは非常に重要です。
すららでは、理解できないまま次に進んでしまうことがなく、苦手な単元を何度でも復習しながらじっくり学べます。
焦らず、マイペースに取り組める環境がしっかり整っています。
メリット4・AI診断×対人コーチングで学習設計が精密
すららは、ただAIが学習履歴を分析するだけでなく、人間の「すららコーチ」とのダブルサポート体制をとっているのが最大の魅力です。
AI診断によって今の理解度やつまずきポイントを数値化し、それをもとにコーチが具体的な学習計画を作成してくれるため、“今の自分にぴったり”なカリキュラムで無理なく続けることができます。
AIの客観的な分析と、コーチによる人間ならではの温かいフォローが合わさることで、機械的すぎず、でも精密な学習支援が受けられるのはすららだけの強みです。
AI+人間コーチのWサポートはすららだけのポイント
AIが「学習の結果」を分析し、コーチが「子どもの性格や状況」を踏まえて計画を立てるというWサポート体制は、他の教材にはなかなか見られません。
どちらか一方では不十分なところを補い合えるのは、保護者にとっても安心できるポイントですね。
AIだけではフォローしきれない細かい学習状況を、コーチが調整してくれる
学習の中で出てくる細かな「気分の波」や「やる気の上下」は、AIだけでは読み取りにくいもの。
すららでは、こうした部分もコーチが丁寧にフォローしてくれます。
「最近やる気が落ちてるから内容を調整しようか」といった柔軟な対応ができるのは、やはり“人の力”があるからこそです。
メリット5・紙を使わず、すべてデジタルでも「記述力」が鍛えられる
「タブレット学習だと記述力が身につかないのでは…?」と不安に感じる保護者の方も多いかもしれません。
ですが、すららでは紙を使わずとも“考えて書く力”を育てる工夫がたくさんあります。
記述問題では、自分の言葉で答えを打ち込む場面も多く、選択肢ではなく文章で答える設問も豊富に用意されています。
答えたあとにはフィードバックや解説も丁寧に表示されるため、「なぜその答えになるのか?」を自分の頭で考えながら学ぶ習慣が身につきます。
記述式の入試や、思考力が問われる新しい学習指導要領にも対応できる力が、自然と育っていくんです。
「論理的に書く力」「説明する力」にフォーカスしたカリキュラム
すららの記述問題では、「なんとなく書く」ではなく、「なぜそう考えたのか」をしっかり言語化することが求められます。
このプロセスが、論理的に考えて書く力を育ててくれるんです。
「なぜ?」「どうして?」に向き合う設問が多く、ただ答えを覚えるだけでは終わらない、深い理解と表現力が身につきます。
これからの教育で重視される“思考力・判断力・表現力”を、自然に育てていける教材です。
読解+記述のトレーニングがデジタル完結でできる教材は珍しい
タブレット教材でここまで本格的な記述トレーニングができるものは珍しく、保護者からも「紙の教材に頼らなくても安心」と好評です。
読み取って、自分の言葉で表現するという力は、入試でも社会でも必要になるスキル。
すららなら、それを日々の学習の中で、無理なく積み重ねていくことができます。
メリット6・途中でやめても「再開」がしやすい
すららは、学習を一時中断しても、そのあとスムーズに再開できるように設計されています。
「最近ちょっと続かない…」「体調が優れなくて休んでいた」という期間があっても、履歴や進捗がしっかり保存されているので、以前の続きからそのまま始めることができます。
とくに、不登校や発達に特性のあるお子さまの場合、どうしても学習のペースに波が出やすいもの。
すららのように、いつでも中断・再開が可能な教材は、安心して続けていくための大きな味方になります。
すららは一時中断→復帰が簡単にできる
ログインすれば、前回どこまで進んでいたかがすぐに表示されるので、「どこから再開したらいいかわからない…」というストレスがありません。
時間が空いてしまっても、自然な流れで学び直せるのは大きな安心ポイントです。
不登校や発達障害の子は「学習ペースに波がある」から、自由に休んで戻れる環境は重要
学びたいときに学べて、休みたいときはしっかり休める。
この柔軟さが、すららのいちばんの強みです。
無理に続けようとしなくていいからこそ、「またやってみようかな」と思える瞬間が生まれます。
学習に“間が空く”ことを責めるのではなく、“戻ってこれる設計”があることが、何より大切なんですよね。
メリット7・出席認定・教育委員会との連携実績がある
すららは、多くの自治体や教育機関で「不登校支援教材」として採用されており、その実績も非常に豊富です。
学校によっては、すららでの学習が「出席扱い」として認定されるケースも増えてきており、実際に通学が難しい子どもたちの学びを支える仕組みとして注目されています。
また、病院内教育や家庭支援にも導入されていて、教育委員会と連携したプロジェクトも進行中です。
学力の維持はもちろん、社会とのつながりを切らさないための“学びの橋渡し”としての役割を果たしてくれているのが、すららの大きな価値です。
すららを使っていると「出席扱い」として学校が認めるケースが多数
すららでの学習履歴はクラウド上に保存され、学校側が確認しやすいようになっているため、「家庭で学んでいること」が証明しやすいのが特長です。
この仕組みを活かして、すららを活用していることを担任や学校に伝えると、出席扱いとして認定される場合も多くあります。
不登校支援教材として、学校や病院と連携しているのはすららならでは
すららは、単なる家庭学習ツールにとどまらず、学校や病院と連携しての学習支援にも積極的に取り組んでいます。
医療的ケアが必要な子どもや、精神的な不安を抱えている子にも、学びの場を提供できる仕組みが整っているのは、すららだけの特長です。
家庭にいながら“社会との接点”を持てることが、子どもにとって大きな安心感につながります。
【すらら】はうざいと言われる原因は何?すららのデメリットについて詳しく紹介します
インターネットで「すらら うざい」というキーワードを見かけて、不安に思った方もいらっしゃるかもしれません。
でも、それは決して教材そのものに問題があるわけではなく、「学び方の相性」や「感じ方の違い」からくるものがほとんどです。
すららには、他にはない魅力がたくさんありますが、だからこそすべての子どもにぴったりとは限らないというのも事実です。
ここでは、「すららがうざいと言われる原因」としてよく挙げられるポイントを、あくまで中立的な視点でご紹介していきます。
合う・合わないを判断する参考にしていただけたらと思います。
原因1・すららコーチやサポートからの連絡がしつこいと感じることがある
すららの特長である「すららコーチ」は、学習の進捗をしっかり管理してくれる反面、少しマメすぎると感じる方もいるようです。
とくに、自分でスケジュールを立てて自由にやりたいタイプの子や、「勉強のことはあまり干渉されたくない」と思っているお子さまにとっては、コーチの声かけやサポートが“過干渉”のように感じてしまうことがあるようです。
もちろん、サポートの頻度やスタイルは相談して調整することもできますので、「うちの子にはどうかな?」と不安に思った場合は、体験中にサポートスタイルを確認しておくと安心です。
自主的にやりたい子や、放っておいてほしい子には合わないこともある
すららは「寄り添い型のサポート」が魅力ではありますが、「自分のペースでやりたい」「あまり声をかけられたくない」というタイプの子にとっては、かえってストレスになってしまうこともあります。
そういった性格の傾向がある場合は、保護者とコーチであらかじめ相談して、サポートの頻度を調整してもらうのが良いかもしれません。
原因2・「やらされ感」が強くなるとプレッシャーに感じることがある
すららでは、AIとコーチが学習計画を立ててくれる仕組みがありますが、それが「親や先生からやらされている」と感じる原因になってしまうこともあるようです。
とくにプレッシャーを感じやすい性格の子は、「スケジュール通りに進めなきゃ…」と焦ってしまい、逆にモチベーションが下がることも。
すららはあくまで“自分のペースで進められる教材”ですが、真面目なお子さまほど「完璧にやらなきゃ」と思いがちなので、その点は周囲のフォローが大切になります。
自動で学習計画を作ってくれるAIに縛られていると感じてしまうことがある
AIが自動的に作成した学習スケジュールは便利ではありますが、「機械にコントロールされてるみたい」と感じてしまうこともあるようです。
そんなときは、コーチと相談して柔軟にプランを変更したり、ゆるめのスケジュールにしてもらうなど、ストレスを減らす工夫をすると、より快適に学習を続けられます。
原因3・キャラクターやナビゲーションが子どもっぽい・くどいと感じることがある
すららの授業には、アニメーションのキャラクターが登場し、会話形式で学習をサポートしてくれます。
多くの子どもにとっては親しみやすく、楽しく学べる要素になっているのですが、学年が上がったり、思春期に差しかかった子どもにとっては、「ちょっと子どもっぽい」「なんだかくどい」と感じることもあるようです。
とくに、ゲームや動画に慣れている現代の子どもたちは、キャラのテンポや話し方に敏感なところもありますので、お子さまの年齢や性格によって合う・合わないが出やすい部分です。
高学年や思春期の子にはキャラクターがうざいと感じることがある
すららのキャラクターは、低〜中学年向けにはちょうど良い設計ですが、高学年や中学生には「子どもっぽく感じる」と受け取られることがあります。
その場合は、保護者が「最初だけで気にならなくなることも多いよ」と声をかけたり、キャラクターの発言を軽く受け流すようアドバイスすることで、うまく乗り越えられることもあります。
原因4・勧誘や営業の印象が「しつこい」と感じる人がいる
すららに限らず、どの通信教材でも資料請求や無料体験を申し込むと、その後に案内や連絡が届くのはよくあることですが、これを「しつこい」「営業っぽい」と感じる方も一定数いるようです。
特にSNS上では、個別の体験談が強調されて拡散されやすく、「勧誘がうざい」といった声が目立ってしまうこともあります。
ただ、すらら側でも不要な連絡を止めたい場合には、しっかり対応してもらえる体制が整っているので、過度な心配は必要ありません。
体験だけ試したい方や、営業を避けたい方は、申し込み時に「連絡はメールのみ希望」などの希望を記載することもできますよ。
「連絡が頻繁」と感じると、SNSでは「うざい」と言われることがある
すららからのフォロー連絡やサポートの案内は、「しっかり見てくれている」と感じる方もいれば、「もう少し距離を置きたい」と感じる方もいます。
そのため、人によってはその対応を「営業っぽい」と感じてしまうことも。
でも、必要ない場合はきちんと止められるので、過度に不安になる必要はありません。
原因5・料金が高く感じる割に効果が実感できない場合がある
すららは、他の家庭学習教材と比べるとやや高めの月額設定になっているため、「これで効果が出なかったらどうしよう…」と心配になる保護者の方も少なくありません。
実際に、子どもが自分から学習に取り組まない場合や、最初だけで続かなくなってしまった場合には、「料金に見合った成果が感じられなかった」という声が出てしまうこともあります。
ただ、すららは「継続してこそ効果を発揮する教材」であるため、子どものタイプやタイミングを見極めて、無理のない導入をすることがとても大切です。
体験期間を活用して、お子さまに合うかどうかを見てから本格的に始めるのが安心です。
子供が1人で学習に取り組めないままだと勉強効果を実感できない保護者もいる
すららは、自学習をベースに設計されているため、最初のうちは親の声かけや見守りが必要になるケースもあります。
完全に“放任”してしまうと、なかなか効果が出にくいことも。
そのため、初期の数週間は「一緒に始める」つもりでサポートし、その後、徐々に自立を促す流れが理想的です。
少しずつでも学習習慣がついてくると、しっかり成果が見えてくるはずです。
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららは高いの?すららの料金プラン詳細
「すらら」って実際どうなの?と調べてみたら、「うざい」とか「高い」といった言葉が出てきてびっくりした…そんな経験をされた方もいるのではないでしょうか。
子どもの教育に関することだからこそ、慎重に選びたいという気持ち、よくわかります。
すららは、一見すると価格が高めに感じられるかもしれませんが、その中には学年を超えて学べる柔軟性や、個別のつまずきに寄り添う仕組みなど、他の教材とは違う価値がたくさん詰まっています。
この記事では、すららの料金プランについて詳しくご紹介しながら、気になる評判の背景や、実際にどんな人に向いているのかをやさしく解説していきます。
すらら家庭用タブレット教材の入学金について
子どもの学習環境を整えたいと考えて、タブレット教材の「すらら」を検討する保護者の方も多いと思います。
その中で最初に気になるのが、やはり入学金の存在ではないでしょうか。
無料体験が主流になっている今の時代に、スタート時から数千円〜一万円以上の入学金がかかるとなると、ちょっと躊躇してしまう気持ちも正直ありますよね。
でも、すららの入学金は、単なる“初期費用”という意味合いだけでなく、子ども専用の学習設計や学習コーチのサポートなど、サービスの質を支える大事な部分でもあるんです。
この記事では、なぜすららに入学金があるのか、そしてそれが他の教材とはどう違うのかを丁寧に解説していきます。
| コース名 | 入学金(税込) |
| 小中・中高5教科コース | 7,700円 |
| 小中・中高3教科、小学4教科コース | 11,000円 |
すらら家庭用タブレット教材/3教科(国・数・英)コース月額料金について
すららを使い始めたいと思ったとき、多くの方が最初に選ぶのが「3教科コース」ではないでしょうか。
国語・算数(数学)・英語という基本的な3科目が学べるこのコースは、小学生から中学生まで、幅広い学年の子どもに対応しています。
ただ、気になるのはその月額料金。
通信教材の中ではやや高めに感じることもあるかもしれません。
でも、その中にはAIを活用した個別学習サポートや、つまずきを見つけてくれる分析機能など、他にはない特徴がぎゅっと詰まっています。
この記事では、3教科コースの具体的な料金や、実際にどんな機能が利用できるのかを詳しく紹介していきます。
毎月支払いコースの料金
すららの利用を検討するとき、まず気になるのが「毎月いくらかかるのか」という点ですよね。
中でも「毎月支払いコース」は、まとまったお金を一度に支払う必要がなく、気軽に始められることから多くの家庭に選ばれているプランです。
初期費用を抑えたい方や、まずはお試し感覚でスタートしたい方にはぴったりの選択肢といえます。
ただし、長期間利用を前提とした場合には、継続コースよりやや割高になるため、どれくらいの期間続ける予定かを事前に考えておくと良いかもしれません。
このセクションでは、毎月支払いコースの具体的な料金や、費用に含まれるサービス内容について詳しくご紹介していきます。
| コース名 | 月額 |
| 小中コース | 8,800円 |
| 中高コース | 8,800円 |
4ヵ月継続コースの料金
すららには、毎月支払いのほかに「4ヵ月継続コース」というプランがあります。
これはあらかじめ4ヵ月分の料金をまとめて支払うことで、1ヵ月あたりの負担が軽くなる仕組みです。
毎月支払いよりも少しお得な設定になっているため、続けて使いたいと考えている方にはおすすめの選択肢です。
特に学習の習慣化を目指す家庭にとっては、4ヵ月という区切りがひとつの目標になりやすく、子ども自身のモチベーションにもつながる場合があります。
ただし、途中でやめたくなったときにどうなるのか気になる方もいらっしゃるかもしれませんね。
この記事では、4ヵ月継続コースの料金体系や、申し込み時に知っておきたいポイントについて詳しくお伝えしていきます。
| コース名 | 月額 |
| 【4ヵ月】小中コース | 8,228円 |
| 【4ヵ月】中高コース | 8,228円 |
すらら家庭用タブレット教材/4教科(国・数・理・社)コース月額料金について
すららの4教科コースは、国語・算数(数学)・理科・社会の学習を一度にカバーできるプランとして、特に中学受験や定期テスト対策を視野に入れたいご家庭に選ばれています。
主要教科のバランスを取りながら、まんべんなく学びたい方にとっては、非常に使い勝手の良い構成になっています。
ただ、その分、月額料金は3教科コースよりも少し高く設定されていますので、「本当に元が取れるのかな?」と迷う方もいらっしゃるかもしれませんね。
でも実際は、AIによる分析機能や無学年方式の柔軟さによって、それぞれの科目で理解度に応じた効果的な学習が可能になります。
ここでは、4教科コースの月額料金や、その価値について詳しく解説していきます。
| コース名 | 月額 |
| 小学コース(毎月支払いコース) | 8,800円 |
| 小中コース(4ヵ月継続コース) | 8,228円 |
すらら家庭用タブレット教材/5教科(国・数・理・社・英)コース月額料金について
すららの中でも最も充実した内容を学べるのが、5教科コースです。
国語・数学・理科・社会・英語の主要科目すべてに対応しており、学校の授業やテスト対策、受験準備まで幅広くカバーできます。
特に、中学生や高校受験を視野に入れた学習をしたいご家庭にとっては、安心して任せられる構成になっているのが特徴です。
月額料金は他のコースよりもやや高めですが、それでも塾に通う費用と比べればかなり経済的ですし、何よりも自宅で自分のペースで学習できる自由さがあります。
ここでは、5教科コースの月額料金の目安や、コストに見合った機能やサポート体制について、わかりやすく解説していきます。
毎月支払いコースの料金
すららを気軽に始めたい方にとって、毎月支払いコースはとても便利なプランです。
初期費用をできるだけ抑えながら、まずは試してみたいというご家庭にぴったりの料金体系になっています。
まとめ払いに比べると月あたりの料金は少し割高ですが、子どもの反応や教材との相性を見ながら続けるかどうかを判断できる点は、大きなメリットですよね。
急な生活の変化にも対応しやすく、学習スタイルに柔軟さを求める方には向いている選択肢だと思います。
ここでは、そんな毎月支払いコースの具体的な料金や、他のプランとの違いについて詳しくご紹介していきます。
| コース名 | 月額 |
| 小学コース | 10,978円 |
| 中高コース | 10,978円 |
4ヵ月継続コースの料金
すららをしばらく続けてみたいと考えている方におすすめなのが、4ヵ月継続コースです。
毎月支払いコースよりも1ヵ月あたりの金額が割安になっており、長期的に使う予定があるご家庭にとっては、コストパフォーマンスの良い選択肢だと思います。
4ヵ月という区切りも、短すぎず長すぎず、子どもが学習習慣を身につけるにはちょうど良い期間ですよね。
まとめて支払う分、最初の出費はやや大きく感じられるかもしれませんが、その分「この期間は頑張ろう」と親子で気持ちをそろえるきっかけにもなります。
ここでは、そんな4ヵ月継続コースの具体的な料金や、メリット・注意点について詳しくご紹介していきます。
| コース名 | 月額 |
| 【4ヵ月】小中コース | 10,428円 |
| 【4ヵ月】中高コース | 10,428円 |
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの勉強効果や勉強効率は?コースについて紹介します
家庭学習教材として注目されている「すらら」。
検索すると「うざい」といったネガティブなワードも目にしますが、その裏側には子どもによって感じ方が異なる教材の特徴があるようです。
実際に使ってみると、想像以上に子どもが前向きに取り組んでいた、という声も多く、教材としての質やサポート体制はしっかりしています。
この記事では、すららがどんなふうに学習効果を発揮してくれるのか、3教科・4教科それぞれのコースごとに分けて、具体的なメリットをご紹介していきます。
「うざい」と感じるか、「わかりやすい」と感じるかは、仕組みを知ることで印象がガラッと変わることもありますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
すらら3教科コース(国・数・英語)の勉強効果について紹介します
家庭での基礎学習に力を入れたい方に人気なのが、すららの3教科コースです。
国語・算数(または数学)・英語の基本となる3科目に絞ることで、苦手を確実に克服し、得意な分野をさらに伸ばすことができます。
AIが子どもの理解度に応じて最適な内容を提案してくれるため、無駄な勉強を省きながら効率よく進められるのも魅力のひとつです。
特に学習習慣がまだ身についていないお子さんでも、ゲーム感覚で進められる設計になっているので、自然と集中力が続くように工夫されています。
このコースでは、どのようにして「わかる力」「使える力」を身につけられるのかを詳しく見ていきます。
勉強効果1・基礎力の定着がとにかく早い
すららの大きな特長は、子ども一人ひとりの理解度に合わせて学べる「無学年方式」にあります。
この仕組みが、基礎の抜けを見逃さず、必要なところを重点的に学習できる環境を整えてくれるんです。
たとえば、つまずきがちな分数や文章読解など、過去に戻って何度でも繰り返し学習できるため、自然と「わかる」実感が積み重なります。
理解できた内容は、定着までがとにかく早く、塾では補えなかった“本人のペース”を大切にできるのが魅力です。
教科書の順番に縛られず、子どもの「今必要なこと」に集中できるからこそ、短期間でもしっかりと基礎が身につきます。
これが、すららの3教科コースが家庭学習に向いている理由のひとつです。
勉強効果2・短時間で「できる→わかる→応用」の流れを作ってくれる
勉強って、わからないまま先に進んでしまうとどんどん嫌になってしまいますよね。
でも、すららはその逆で「できた!」「わかった!」という小さな達成感を繰り返すことで、やる気を引き出す仕組みになっています。
映像授業で要点をコンパクトに学び、すぐに確認問題に取り組むことで「わかったつもり」ではなく「本当に理解できた」と感じられる流れが自然とできあがります。
さらに、その理解をもとにした応用問題にもチャレンジできるので、短い時間でもしっかり力がついている実感が持てるんです。
だらだらと勉強させるのではなく、集中して取り組み、効率よく成果を出したいというご家庭にはぴったりの設計です。
勉強効果3・中学生は主要3教科で内申点が決まるから「点数を上げたい」「定期テストで成果を出したい」という目的に直結する
中学生になると、学校の内申点や定期テストの結果が、進路に大きく関わってきます。
中でも国語・数学・英語の3教科は配点が高く、成績全体に与える影響が大きい教科です。
すららの3教科コースでは、それぞれの教科で「どこが弱いか」「どの単元に戻るべきか」が明確になるので、効率よく弱点を補強できます。
学年をまたいで学習できる仕組みだからこそ、前の学年の理解不足が原因だった場合にも、すぐに戻って学び直せるのが心強いです。
「とにかくテストの点数を上げたい」「通知表を良くしたい」と思っている保護者にとって、すららのサポートは非常に実用的なものになっています。
すらら4教科コース(国・数・英語・理科または社会)の勉強効果について紹介します
主要3教科に加えて、理科または社会のどちらかをプラスできるのが、すららの4教科コースです。
理科や社会は暗記だけでは対応しきれない教科でもあり、用語や流れを理解しながら学ぶ必要があります。
すららでは、こうした科目もアニメーションやストーリー仕立ての解説で学べるため、ただの詰め込みにならず、自然と「面白い」と感じながら学習できるのが特徴です。
とくに中学生にとっては、定期テストで得点源になりやすい理科・社会を早いうちからしっかり対策しておくことはとても重要ですよね。
ここでは、すららの4教科コースがどのように学習効果を発揮してくれるのかを、具体的に紹介していきます。
勉強効果1・理科・社会は、「繰り返し学習」と「確認テスト」で記憶の定着率が高まる
理科や社会のような教科は、内容を一度学んだだけではなかなか頭に残りにくいものです。
すららでは、まずストーリー性のある動画やアニメーションで内容を理解し、そのあとで確認テストを通じて定着を図る流れがしっかりと組まれています。
この「インプット」と「アウトプット」をバランスよく繰り返すことが、記憶を深く定着させる秘訣なんです。
とくに社会の年号や理科の用語など、丸暗記では苦痛になりがちな単元も、すららなら視覚的に理解しやすくなっているため、楽しみながら覚えることができます。
何度でも復習できる設計なので、テスト前の総まとめにも効果的に活用できるのが嬉しいですね。
勉強効果2・ポイントを押さえた要点学習で、時間対効果がとてもいい
すららでは、理科・社会においても「どこが大事なのか」「どこで点が取れるのか」という要点を明確にした学習ができます。
授業動画もポイントごとに整理されていて、長々と見続ける必要がなく、集中しやすいのが特徴です。
無駄を省いた構成なので、理解したい部分だけを効率よくピックアップでき、時間あたりの学習効率がとても高いと感じます。
特に、理科や社会のように暗記に頼りがちな教科では、「ただ覚える」よりも「要点を理解して関連づける」学び方が必要です。
すららは、要点を抑えた短時間集中型のスタイルで、子どもにとっても負担を感じにくく、取り組みやすい教材になっています。
勉強効果3・通常の塾や学校より、短時間で理解→テスト対策ができるところが強み
学校や塾では、限られた時間の中で一斉に進む授業スタイルが基本ですが、すららは「今の自分に必要な学び」に集中できるので、学習の効率が大きく変わってきます。
たとえば苦手な単元に絞って何度も復習したり、得意な単元はスピーディに進んだりと、ムダのない学習が可能です。
テスト前も、自分が得点しやすい単元を中心に復習できるので、短時間で確実に点数アップが狙えるのが大きな魅力です。
時間に追われがちな中学生や、部活と両立したいお子さんにもぴったりのスタイルで、「塾より効率がいい」と感じる保護者の声も増えています。
自分に合わせたテスト対策ができることこそ、すららの強みです。
すらら5教科コース(国・数・英語・理科・社会)の勉強効果について紹介します
主要5教科すべてを網羅したすららのフルコースは、「内申点を上げたい」「高校受験を見据えて学力を底上げしたい」と考えているご家庭にとって、非常に心強い学習プランです。
国語・数学・英語・理科・社会の全科目に対応しており、それぞれにAIが学習設計を行ってくれるので、まさに“すべてを任せられる家庭教師”のような存在です。
学校の進度に左右されず、子どもの理解度に合わせて自由に進められるのが特長で、家庭学習の質を大きく引き上げてくれます。
ここからは、5教科コースならではの勉強効果について、さらに詳しく見ていきましょう。
勉強効果1・全教科を満遍なくカバーし、内申点・通知表UPに直結 / 特に中学生の内申点は「5教科バランス型」が必須
中学生の内申点は、主要5教科の評価が大きく影響します。
得意な教科だけではバランスが悪く、苦手な教科を放置してしまうと内申点が思ったように伸びません。
すららの5教科コースでは、すべての教科を無理なく横並びで学べるため、学力の偏りが少なく、通知表全体の底上げに直結しやすくなります。
学校のテスト範囲や授業内容に合わせた進度調整も可能なので、内申対策としても非常に効果的です。
また、教科ごとのつまずきをAIが見つけてくれるので、「どこから手をつければいいのか分からない」と悩むこともありません。
全体的な学力を底上げしながら、評価につながるポイントを押さえていけるのが大きなメリットです。
勉強効果2・高校受験にも直結する実力アップ / 模試や過去問対策にも応用できる
高校受験を見据えた勉強では、単なる定期テスト対策だけでなく、応用力や思考力も求められます。
すららの5教科コースでは、教科書レベルをしっかり理解したうえで、模試や入試問題に対応できる実力も養える構成になっています。
たとえば、基本問題から発展問題まで段階的にステップアップできるしくみや、AIが苦手分野を自動分析してくれる機能によって、「どこを強化すればいいのか」が明確になるのがポイントです。
単元をまたいで出題されるような複合的な問題にも対応できる実力が身につくため、受験対策としての信頼度も高いです。
基礎から入試レベルまでを一貫して学べるのが、この5教科コースの大きな魅力です。
勉強効果3・5教科すべてAIが自動で弱点を分析し、学習計画を立ててくれるから効率的
5教科をまんべんなく勉強する中で、「どこが苦手か分からない」「勉強計画が立てられない」といった悩みを感じる子も多いですよね。
すららでは、AIが日々の学習結果をもとに、自動でつまずきポイントを分析し、効率よく学習を進めるための個別プランを提示してくれます。
特に5教科ともなると、親がすべてを把握してサポートするのは大変ですが、すららなら自動でバランスよく進行してくれるので安心です。
理解度に合わせて内容が変わることで、勉強のムダも省け、時間を有効に使えるようになります。
学年に関係なく、今の子どもに必要な学びだけに集中できるこの仕組みは、他の教材にはない強みです。
勉強効果4・他の教材や塾より、時間あたりの学習効果は高いと感じる人が多い
すららを使っている保護者や子どもたちの声として多いのが、「時間あたりの効果が高い」という実感です。
これは、必要な学習だけに集中できる無駄のない設計と、わかりやすい解説、すぐに実践できる演習がセットになっているからこそ得られるものです。
塾では移動や待ち時間も含めると意外と学習時間が限られてしまいますが、すららならタブレットひとつでいつでもどこでも始められるため、時間を最大限に活かせます。
短時間でも「わかる」「解ける」実感が得られるので、学習意欲の維持にもつながりやすく、勉強が苦手な子にとっても続けやすい環境です。
効率重視の家庭学習をしたい方にとって、すららはとても頼れる存在です。
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららは不登校や発達障害でも安心・安全に使える理由
「すらら」という教材を検索すると、時々目にするのが「うざい」「使いにくい」といったネガティブな言葉。
でも、それは一部の使い方や印象だけを切り取ったもので、実際は発達特性のあるお子さんや、不登校の生徒にとって非常にやさしい設計になっている教材なんです。
すららは学年の枠にとらわれず、自分のペースで学べる無学年方式を採用していて、さらに対人関係のストレスが一切ないのも特長です。
この記事では、発達障害や不登校の子どもたちでも安心して使える理由を、「本人のペース」「非対面の安心感」「ユニバーサルデザイン」の3つの観点から、わかりやすくご紹介していきます。
安全な理由1・「本人のペースで学習できる」からプレッシャーがない
すららの魅力は、子どもが自分のペースで学習を進められる点にあります。
学校や塾では「みんなと同じスピードで進むこと」が求められがちですが、すららでは理解度に合わせて進度を調整できるので、焦る必要がありません。
苦手な単元はじっくり取り組み、得意な分野はスムーズに進めるといった学習スタイルが可能です。これにより「遅れている」と感じるプレッシャーや「ついていけない」という不安がなくなり、安心して学習を続けやすくなります。
さらに、復習と予習を自由に組み合わせられるため、学校の授業で理解できなかった内容を補うこともできます。
本人のペースを大切にする仕組みがあるからこそ、学ぶこと自体を前向きに捉えやすくなり、自然と学習意欲が育っていくのです。
学校の授業の「遅れ」や「先取り」を気にせず、マイペースに学べるから、ストレスが少ない
すららの最大の魅力のひとつが「無学年方式」です。
これは、学年にとらわれず今の理解度に応じて学べる仕組みで、学校の授業で感じる「みんなより遅れているかも…」というプレッシャーや、「もっと先に進みたいのに」という焦りを感じる必要がありません。
学習内容はいつでも戻れるし、先にも進めるので、自分のペースを大切にできるんです。
特に発達特性のあるお子さんにとっては、この“他人と比べなくていい”環境は、心の安心感にもつながります。
焦らず、マイペースに学び続けられる環境が整っていることで、学習に対するストレスがぐっと減ると感じるご家庭も多いようです。
ADHDタイプの子は「集中できる時に一気に」、ASDタイプの子は「毎日決まったペースで」、それぞれに合った使い方ができる
すららは、「自分のペースで進められる」だけでなく、その日の気分や集中度に合わせて柔軟に取り組み方を変えられるのも大きな魅力です。
たとえば、ADHD傾向のあるお子さんは集中力が長く続かないことが多いですが、「今日は集中できそう!」というタイミングに一気に進めることで、無理なく学習が進みます。
一方で、ASD傾向のあるお子さんは、決まった時間・決まった順番で取り組むことに安心感を持つことが多いため、毎日決まったペースでログインして、同じ流れで学習を進めることで安定感を得られます。
すららの設計は、こうした多様な特性に対して自然にフィットする柔軟さがあるから、安心して使えるんです。
安全な理由2・「対面の緊張や不安がゼロ」だから取り組みやすい
就職活動の中で大きなハードルになるのが「面談や面接の緊張」です。特に対面だと表情や仕草が気になったり、言葉に詰まってしまう不安から力を発揮できない方も少なくありません。
その点、dodaチャレンジをはじめとしたオンライン面談やカウンセリングは、自宅など落ち着いた環境から参加できるため、余計なプレッシャーを感じにくいのが特徴です。
実際に「画面越しだから話しやすかった」「顔を合わせる緊張がなく安心できた」という声も多くあります。対面の場で緊張してしまい、自分の希望や配慮事項をうまく伝えられなかった経験がある方にとって、オンライン形式は非常に取り組みやすい選択肢です。
自分のペースで話せることで、就職活動そのものに前向きに取り組めるようになる点が大きなメリットです。
アニメーションのキャラが優しく教えてくれて、正解でも不正解でも感情的な反応をされることはない
すららの授業は、可愛らしいアニメーションのキャラクターがナビゲートしてくれるスタイルで進行します。
リアルな先生のように感情的に反応されることがないので、「間違えたら怒られるかも…」「答えを間違えるのが怖い」といった不安を感じずに、のびのびと学べるのが魅力です。
子どもにとって「安心して間違えられる環境」というのは、実はとても大切なこと。
特に人前で発表が苦手な子や、緊張しやすい性格の子には、こうした環境があるだけで勉強へのハードルがぐっと下がります。
優しく声をかけてくれるキャラクターたちが、学習をサポートしてくれる存在として自然に寄り添ってくれるのも、すららのやさしさです。
人とのコミュニケーションに不安がないから安心して学ぶことができる
発達障害や不登校の子どもたちの中には、「人と話すのが怖い」「先生の目が気になる」といったコミュニケーションに対する不安を抱えている子が少なくありません。
すららはそういった対人ストレスが一切ないため、安心して学びに集中できる環境が整っています。
誰かと話す必要もなく、自分だけのペースで、静かに取り組めることが大きな安心材料になるんです。
自分のタイミングで、必要なときにだけサポートを受けられる仕組みになっているので、無理に誰かと関わることなく、自立した学習習慣を身につけられます。
特に集団授業に抵抗がある子には、こうした環境が学習への第一歩として非常に有効だと感じます。
安全な理由3・発達障害に対応した「ユニバーサルデザイン」設計
すららは、単に“使いやすい教材”というだけでなく、発達障害のある子どもたちにも配慮されたユニバーサルデザインで設計されているのが特長です。
画面の文字サイズや配色、音声のトーン、操作方法など、すべてが「ストレスなく使える」よう細かく工夫されています。
たとえば、画面の切り替えが急でないことや、視覚的なノイズが少ないことなど、感覚過敏を持つ子にも配慮されている部分が多くあります。
また、学習の進捗状況もシンプルに表示されていて、「今どこにいるのか」「次は何をすればいいのか」が一目でわかるので、不安を感じずに取り組み続けることができます。
細かなところまでやさしさが行き届いた設計だからこそ、すららは安心しておすすめできる教材です。
すららは「誰でも理解しやすく、つまずきにくい」ように作られている
すららの教材は、学年や発達段階に関係なく「どの子でも分かりやすく学べる」ことを前提に作られています。
説明は簡潔かつ丁寧で、難しい言葉を避けながら、子どもがつまずきやすいポイントをしっかり押さえてくれます。
画面の操作も直感的で、初めての子でもすぐに使いこなせるほどシンプルです。
さらに、解説のテンポや画面遷移のスピードもゆったりしているので、焦らされることなく落ち着いて学べます。
「分からないまま置いていかれる」という不安がなく、「次もやってみよう」と思える安心感があることが、継続につながっているのだと思います。
誰にとっても“やさしい”作りが、すららの大きな魅力です。
読字障害(ディスレクシア)、言語理解に時間がかかるASDの子にも分かりやすい
読み書きに困難を感じるディスレクシアのお子さんや、言葉の理解に時間がかかるASDタイプの子にとって、一般的な教材は情報の処理量が多すぎて、負担に感じることも多いですよね。
すららは、文章だけに頼らず、音声やアニメーション、イラストなどを活用して視覚的にも聴覚的にも情報が入るようになっているので、言葉だけで理解する必要がありません。
また、一つひとつの説明が短く区切られていて、ステップごとに確認できる構成なので、集中が切れやすい子や、理解に時間がかかる子にとっても取り組みやすいです。
「自分にもできる!」と実感しながら学べることが、安心と継続のポイントになっています。
「視覚優位」「聴覚優位」どちらのタイプの子にもマッチしやすいのが特長
子どもによって得意な感覚はさまざまです。
目で見て理解しやすい「視覚優位」の子もいれば、音で聞くことで内容が頭に入りやすい「聴覚優位」の子もいます。
すららは、どちらの特性にも対応できるよう、映像・文字・音声をバランスよく組み合わせた設計になっているので、自分に合ったスタイルで無理なく学習を進めることができます。
アニメーションやイラストを多用する一方で、すべての文章に音声がついているため、読み書きが苦手な子でも「聞いて理解する」ことが可能です。
こうした多感覚に対応した教材設計は、学び方に個人差がある発達特性の子どもにとって、大きな安心材料になります。
「音声速度」を調整できる機能もあるから、「ゆっくり聞きたい」「早く進めたい」など、子どもの特性に合わせられる
すららには、学習をより自分らしく進められるよう「音声の再生速度」を調整できる機能が備わっています。
言葉の理解に時間がかかる子には、音声をゆっくりにしてじっくり聞かせることで、焦らず確実に内容を理解することができます。
一方で、同じ説明を何度も聞くのが苦手な子や、テンポよく進めたい子には、再生速度を少し上げてスムーズに進むことでストレスなく学べます。
このように、「一律のスピード」で教えるのではなく、「その子にちょうどいい速さ」で進められる柔軟さが、すららの大きな特長です。
自分に合わせられることで、学習へのモチベーションも自然と保ちやすくなります。
安全な理由4・間違えても怒られない・恥をかかない設計
就職活動や学習の場では「もし間違えたらどうしよう」「恥ずかしい思いをしたら嫌だ」という不安が大きなストレスにつながることがあります。
特に面接や対面でのやり取りでは、答えを間違えたときに相手の反応が気になってしまい、自信を失ってしまう方も少なくありません。その点、dodaチャレンジのサポートや一部の学習システムは「間違いを責めない設計」がなされており、安心して挑戦できるのが特徴です。
間違えてもすぐに訂正できたり、改善点をやさしくフィードバックしてくれるため、失敗を恐れずに練習や準備を進めることができます。
このような環境は「挑戦すること自体が学びになる」と考えられており、緊張しがちな方や失敗経験がトラウマになっている方にとって特に心強いサポートになります。怒られたり恥をかく心配がないことで、自分のペースで安心して成長できるのです。
「否定」ではなく「納得」させてくれるから、自己肯定感が下がりにくい
すららでは、間違えたときに「不正解!」と責めるような表現は一切ありません。
代わりに、なぜ間違えたのかを優しく説明してくれたり、もう一度チャレンジできる仕組みが整っているので、子どもが「失敗=悪いこと」と感じにくくなっています。
特に自己肯定感が下がりやすい特性のある子にとって、「間違っても大丈夫」と思える環境はとても大切です。
学びのなかで失敗はつきものですが、すららはその失敗を責めることなく、学びのチャンスに変えてくれるので、子どもが前向きな気持ちで学習を続けやすくなります。
「できた」にも「できなかった」にも、優しく寄り添う教材だからこそ、安心して取り組めるのだと思います。
学校や塾では感じがちな「恥ずかしい」「できない」といったネガティブ感情を抱きにくい
集団授業の場では、発言やテストの結果が目立つことで「できなかった自分」を強く意識してしまうことがありますよね。
特に発達特性を持つ子どもは、そのプレッシャーから学習に苦手意識を抱いてしまうことも少なくありません。
すららは、自分ひとりで取り組める環境なので、人の目を気にせずにチャレンジできるのが大きな安心ポイントです。
間違えても誰かに見られることはなく、「できなかったから恥ずかしい」と感じることもありません。
こうした“失敗しても誰にも責められない”環境は、安心して学びに向かうための土台になります。
すららは、学習を「競争」ではなく「自分の成長」として受け止めやすくしてくれる教材なんです。
安全な理由5・「ゲーム感覚」の楽しい仕組みで続けやすい
すららは単なる「勉強アプリ」ではなく、子どもが楽しく続けられる工夫が満載の教材です。
クイズ形式で出題されたり、キャラクターと一緒に進めたり、ポイントを貯めてごほうびがもらえるような仕組みもあるので、自然と「もう少しやってみようかな」という気持ちになれます。
特に集中力が続きにくい子や、勉強に苦手意識のある子でも、「楽しいから続けられる」「ゲーム感覚で気づいたら進んでた」と感じることが多く、勉強というより“体験”に近い感覚で学べるのが魅力です。
「机に向かうのが苦手」というお子さんでも、タブレットなら気軽に取り組みやすく、日々の学習習慣づくりにもつながります。
アニメキャラクターがナビゲートし、クイズ形式やゲーム感覚の要素があるから「もうちょっと続けたい」と思わせる工夫がされてる
すららの魅力のひとつが、「勉強を遊びのように楽しめる」工夫がたくさん詰まっているところです。
授業をナビゲートしてくれるのは、親しみやすいアニメキャラクターたち。
彼らがやさしく声をかけてくれることで、ひとりで学んでいる感じがなく、安心感とともに学習が進められます。
また、問題もクイズ形式で出題されることが多く、ちょっとしたゲーム感覚で取り組めるので、苦手意識を持っていた教科でも「気づけば集中していた」という子どもが少なくありません。
こうした「もうちょっとだけやってみようかな」と思える仕掛けがあることで、無理なく学習が習慣化していくのも、すららの大きな魅力です。
ADHDの子は「すぐに褒められる」「すぐに結果が出る」とやる気が続きやすい傾向がある
ADHD傾向のあるお子さんは、長時間集中を保つことが難しい一方で、「すぐに反応がある」「すぐに成果が見える」といった“即時性”のある刺激には反応しやすい特性を持っています。
すららでは、問題を解くたびにキャラクターが褒めてくれたり、正解が即座に表示されたりと、ポジティブなフィードバックがすぐに得られる仕組みが整っています。
これが「もっとやりたい」「次も頑張ろう」と感じさせてくれる原動力になるんです。
小さな成功体験の積み重ねが、学習への自信や自己肯定感につながり、結果的に勉強が楽しいものとして定着していきます。
こうしたやる気を引き出す工夫は、すららならではの強みです。
安全な理由6・「すららコーチ」がいるから親子で抱え込まなくていい
家庭学習を続ける中でよくあるのが「親子で衝突してしまう」という悩みです。親は子どものためを思って声をかけていても、子どもからするとプレッシャーに感じたり反発したくなったりすることがあります。
その結果、学習そのものよりも親子関係がストレスの原因になってしまうケースも少なくありません。その点、すららには「すららコーチ」という専門のスタッフが伴走してくれる仕組みがあり、学習計画の立て方や進め方を親子に代わってサポートしてくれます。
保護者も「全部を自分が背負わなくてもいい」と安心できますし、子どもも第三者のアドバイスを受け入れやすくなるため、学習がスムーズに進みやすくなります。親子だけで抱え込まなくてよい仕組みがあることで、学習環境がより安心で安全なものになるのです。
ADHDやASD、学習障害の特性を理解した対応をしてくれるコーチが多い
すららでは、教材をただ提供するだけでなく、学習をサポートしてくれる「すららコーチ」がついているのが特長です。
このコーチたちは、発達障害や学習障害に理解があり、ADHDやASDのお子さんへの対応にも慣れているスタッフが多く在籍しています。
保護者だけで悩みを抱え込む必要がなく、第三者の専門的な視点からアドバイスがもらえるのは、本当に心強いサポートです。
どんなふうに声をかけたらよいか、やる気が出ないときの対応など、発達特性に合った具体的なアドバイスをもらえることで、家庭の中のストレスも軽減されることが多いようです。
こうした体制があるからこそ、継続できるご家庭もたくさんあるのです。
コーチが学習計画を立てたり、つまずきポイントを教えてくれる
「何をどの順番でやらせればいいのか分からない」「今、どこでつまずいているのかが見えにくい」と感じる保護者の方も多いと思います。
すららでは、すららコーチが定期的に学習進捗をチェックしてくれて、お子さんに合った学習計画を立ててくれるので、家庭学習の方向性がとてもクリアになります。
また、どの単元で理解が止まっているのか、苦手がどこにあるのかもデータで明確になるので、「ここを重点的に復習しましょう」といったアドバイスがすぐにもらえるんです。
コーチのサポートがあることで、親子での関係に摩擦を生みにくくなり、自然な距離感で学習を見守ることができるのも嬉しいポイントです。
安全な理由7・「完全オンライン」だから家で完結できる
学習や就職活動のサポートを受けるときに、通所や通学が必要だと移動の負担や人との関わりに不安を感じてしまう方も多いです。
特に体調が安定していないときや外出が難しいときには「行くだけで疲れてしまう」「途中で続けられなくなる」という心配もあります。
その点、「完全オンライン」で利用できるサービスであれば、自宅からすべてを完結できるため安心です。
例えば、すららの学習やdodaチャレンジのオンライン面談も、自宅のパソコンやタブレットを使って受けられるので、外出の手間がなく、気持ち的にもリラックスした状態で取り組むことができます。
移動のストレスがないだけでなく、家庭の環境に合わせて自分のペースで進められるため、無理なく継続できるのが大きなメリットです。
「家で安心して完結できる」という点は、安全で取り組みやすい理由のひとつになっています。
タブレット1台あればできるから、環境づくりもシンプルだし、親の負担も減る
すららは、インターネット環境とタブレットやパソコンが1台あれば、すぐに学習をスタートできる「完全オンライン教材」です。
教材の到着を待ったり、通塾の送り迎えをしたりといった手間が一切なく、すべてが自宅で完結するので、忙しいご家庭や親御さんにとっては本当に助かる存在です。
特に発達障害のあるお子さんの場合、通塾の準備や移動そのものがストレスになることもありますが、自宅で落ち着いた状態で学べることで、学習効率もぐんと上がります。
また、教材の出し入れやノート整理なども必要最小限なので、親の負担も少なく、家庭内のイライラも減らせるのが嬉しいですよね。
通学できない間も学習の「穴」を作らず、自信を持たせてあげられる
不登校や体調の問題などで学校に通えない期間があると、「勉強が遅れてしまうのでは?」と心配になる方も多いですよね。
すららなら、そういった不安をしっかりカバーしてくれます。
自宅にいながら、教科書の内容に準拠したカリキュラムで学べるので、学校と同じペース、あるいは自分に合ったペースで学びを進めることができます。
「他の子と差がついてしまう」というプレッシャーがなくなり、安心して継続することができるため、自己肯定感の低下も防ぎやすいです。
通学が難しい間も、「自分はちゃんと頑張れている」と実感できる環境があることで、子どもの自信にもつながります。
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの退会方法・解約方法について紹介します
家庭用学習教材として多くの家庭に支持されている「すらら」ですが、使っていくうちに「一時的にお休みしたい」「もう利用しなくなったかも」と感じるタイミングが来ることもあるかもしれません。
そんなときに気になるのが、「解約」や「退会」の手続きです。
SNSや口コミで「すららは解約しづらい」「退会方法が分かりにくい」といった声を見かけて、少し不安になる方もいるかもしれませんね。
でも実際には、すららの手続きはそれほど難しいものではなく、ルールに沿って正しく進めればスムーズに完了できます。
ただし、“解約”と“退会”には明確な違いがあるため、その意味を正しく理解しておくことがとても大切です。
この記事では、それぞれの違いや手順をわかりやすくご紹介していきます。
すららの【退会】と【解約】は意味が異なる!それぞれの違いについて解説します
すららをやめようと思ったときに、まず注意しておきたいのが「解約」と「退会」はまったく別の意味を持つということです。
どちらも「やめる」というイメージがありますが、手続きをした後の状況や影響が大きく違ってきます。
たとえば、「解約」は月額の支払いを止めて一時的に教材の利用を中断すること。
一方、「退会」はすららの会員そのものをやめ、登録情報や学習データなどもすべて削除されるものです。
今後また利用する可能性がある場合には、退会ではなく解約を選んだほうが安全ですし、「完全にすららを卒業したい」と思っているなら退会を選ぶことになります。
それぞれの違いをしっかり押さえて、自分に合った方法を選びましょう。
すららの解約は「利用を停止すること」。
毎月の支払い(利用料)を止める手続き。
解約とは、すららの利用を一時的に中断するための手続きで、毎月発生している利用料の支払いをストップすることを指します。
たとえば「部活が忙しくなった」「一旦お休みしたい」といった事情がある場合、この方法を選ぶことで、学習サービスを停止しつつも、会員情報や学習履歴などはそのまま残しておくことができます。
つまり、解約後もアカウント自体は残っているため、将来的に「もう一度始めようかな」と思ったときに、すぐ再開できるのが大きなメリットです。
データが消える心配がないので、迷っている方や再開の可能性がある方には、まず解約から検討するのがおすすめです。
すららの退会は 「すららの会員そのものをやめること」。
データも消える。
退会の手続きは、すららのサービス自体を完全に終了させるためのものです。
この手続きを行うと、アカウントや登録情報はもちろん、これまでの学習履歴や成績データもすべて削除されてしまいます。
そのため、「もうすららを使うつもりはない」と明確に決めている方には向いている方法ですが、もし「またいつか使うかも」と少しでも思っているなら、慎重に検討する必要があります。
退会すると元の状態に戻すことはできず、新たに始める際には新規登録からやり直しになる点も注意が必要です。
すららは子どものペースに寄り添って使える教材なので、続けるかどうか迷っている段階なら、無理に退会を選ばず、まずは解約にとどめておくのが安心です。
すららの解約方法1・すららコール(サポートセンター)に電話
すららの解約を希望する場合は、Webサイトのマイページなどからボタンひとつで完了するタイプではありません。
すららでは、専用のサポート窓口「すららコール」への電話で手続きを行う必要があります。
電話というと少し面倒に感じるかもしれませんが、オペレーターが丁寧に案内してくれるので心配はいりません。
電話をかける際には、登録している保護者の氏名、メールアドレス、生徒IDなどの情報を手元に用意しておくとスムーズです。
手続きにかかる時間は数分程度で、しつこく引き止められるようなことも基本的にはありません。
受付時間は平日9時〜18時が基本となっているので、余裕のある時間帯を選んで連絡するのがおすすめです。
| 【すららコール】
0120-954-510(平日10時~20時 土日祝休み) |
すららの解約はメールやWEBからは受け付けていない
すららを解約する際に気をつけたいのが、「WEBやメールでの解約手続きはできない」という点です。
多くのサービスではオンライン上で手続きが完結することが多いため、すららでも「マイページからできるのでは?」と思われがちですが、実際には専用のサポート窓口に電話で連絡する必要があります。
このあたりはややアナログに感じるかもしれませんが、逆に言えば、対面で確認を取りながら進められる分、安心感もあります。
うっかりミスや誤解を防ぐためにも、電話で丁寧に説明を受けながら手続きを進める流れが整っています。
もしも「電話が苦手…」という方は、事前に聞きたい内容や伝える情報をメモしておくと安心して手続きできますよ。
すららの解約方法2・電話で本人確認/登録者氏名・ID・電話番号など
すららの解約手続きでは、電話口での本人確認が必要となります。
解約したい旨を伝えたあと、オペレーターから登録者情報の確認を求められるため、あらかじめ「契約者氏名」「会員ID」「登録電話番号」などを手元に準備しておくとスムーズです。
こうした確認作業は、セキュリティ面でも大切なプロセスで、間違って他人のアカウントに干渉されないようにするためのものです。
万が一、登録情報を忘れてしまった場合も、オペレーターが丁寧に確認してくれるので焦る必要はありません。
少しの手間はかかりますが、安心して手続きを進められるような仕組みがきちんと整っている印象です。
すららの解約方法3・解約希望日を伝える/日割り計算はされません
すららの解約手続きが進んだら、次に大切なのが「解約希望日を伝える」ことです。
基本的には月額料金制となっており、解約したい月のいつ申し出をしても、その月の料金は全額請求されます。
つまり、日割りでの返金や減額は行われない仕組みになっているため、なるべく月末に近づく前のタイミングで手続きを行うのがベストです。
「もう使わないかも…」と感じた時点で早めに動くことが、無駄な出費を避けるポイントになります。
解約希望日をしっかり伝えることで、翌月の自動更新を防げるので、電話の際にはその点をしっかり確認しましょう。
わかりにくい点があれば、遠慮なくその場で質問するのもおすすめです。
すららの退会方法について/解約手続き完了後に退会依頼をする
すららでは、解約と退会が別の手続きとして扱われています。
月額の支払いを止めて教材の利用を停止する「解約」が済んだあと、さらに会員データそのものを削除する「退会」も希望する場合には、追加でその旨を伝える必要があります。
退会の手続きも解約と同じく電話で行いますが、必ずしも退会をしなければならないわけではありません。
解約後もアカウントや学習履歴を残しておきたい方は、退会せずそのままにしておくのが一般的です。
万が一「またすららを使いたい」と思ったときに、スムーズに再開できるようにしておきたい場合は、退会せずにデータを保持しておくのがおすすめです。
すらら解約の電話時に退会希望の旨を伝える
退会を希望している場合は、解約の電話をするタイミングでそのまま「退会もしたいです」と伝えることができます。
解約と退会は別の扱いとはいえ、電話口で一緒に処理してもらえるので、手続きが二重になることはありません。
オペレーターが解約と退会の違いを丁寧に説明してくれるため、もし「まだ迷っている…」という場合でも、その場で相談しながら決めることができます。
退会することで学習履歴や登録情報がすべて削除されるため、本当に必要かどうかを一度考えてから判断すると安心です。
「また始めるかもしれない」と感じている場合は、退会をせず、まずは解約のみにとどめておく選択もアリですよ。
すらら解約後に退会をしなくても全く問題はありません(料金の支払いは停止します)
すららでは、解約の手続きを完了すれば、月額の料金はきちんと停止されます。
そのため、退会の手続きを行わなかったとしても、追加で費用が発生することはありません。
「データを残しておきたい」「また再開するかもしれない」という方には、退会せずそのままにしておく方法がおすすめです。
解約後もアカウント自体は維持されるため、ログインすれば過去の学習記録を確認することも可能です。
再開を希望する際は、コースを選んで支払いを再開するだけなので、とてもスムーズです。
迷っている場合は、まずは解約だけにして、退会の判断は後からゆっくり行っても問題ありません。
【すらら】はうざい!?小学生家庭用タブレット教材すららの効果的な使い方について紹介します
すららは、子どもの理解度に応じて学習を進められる無学年式タブレット教材です。
「うざい」「続かない」という声も時折見かけますが、それは多くの場合、使い方や期待値のズレに原因があるように感じます。
すららは、自分のペースで進められる自由度の高い教材だからこそ、上手に活用するには“コツ”が必要なんです。
年齢や学年によって、最適な使い方も変わってくるので、小学生・中学生それぞれの効果的な活用法を知っておくことが大切です。
このページでは、すららの良さを最大限に引き出すための使い方を、学年別に分かりやすくご紹介していきます。
お子さんの学習をサポートするヒントとして、ぜひ活用してみてくださいね。
【小学生】すららの効果的な使い方について紹介します
小学生は、集中力が続く時間も短く、学習のモチベーションを保つのが難しい時期でもあります。
すららはそんな小学生にもぴったりな「短時間集中」や「視覚的に楽しい」学び方ができる教材です。
とくに低学年では、親の関わり方が継続のカギになるため、親子で楽しむ姿勢も大切です。
また、すららにはAIが苦手を自動で分析してくれる機能もあるため、ただ漫然と使うのではなく、「どこを補強すべきか」を明確にしてから使うと、より効果的な学習につながります。
ゲーム感覚の要素やごほうび制度などをうまく取り入れながら、楽しくコツコツ続ける工夫がポイントです。
使い方1・「短時間×頻度」でリズムを作る/1回20〜30分を目安に、毎日少しずつ続ける
すららを小学生が無理なく継続するためには、「1回あたりの学習時間を短く、頻度を高く」するのがポイントです。
集中力が長く続かない年齢だからこそ、1日20〜30分ほどの短時間学習を毎日積み重ねていくほうが、成果が出やすいです。
すららのユニット構成は1回で終えられる長さになっており、「今日はここまで!」とゴールが見えることで達成感が生まれやすくなっています。
最初から長時間の学習を求めず、短くても「毎日触れること」を意識していくことで、学習習慣が自然と身についていきます。
無理のないリズムを作ってあげることが、継続への一番の近道です。
使い方2・「ごほうび制度」を活用する/1ユニット終わったらシールを貼るとか、小さな達成感を演出すると、やる気が続く
「すららやってね」と言うだけでは、なかなか子どもは自発的に動いてくれませんよね。
そんなときに効果的なのが、小さな“ごほうび”です。
たとえば、1ユニット終わるごとにカレンダーにシールを貼る、3日続けたら好きなおやつをあげるなど、子どもが「やった!」と実感できる演出を加えるだけで、モチベーションが大きく変わります。
すららには達成度が表示されるので、目に見える進捗と組み合わせて、ごほうびの仕組みを取り入れてみると、学習が“楽しみ”へと変わっていきます。
特に低学年のうちは、このような楽しい仕掛けが継続の後押しになってくれますよ。
使い方3・親も一緒に楽しむ姿勢を/とくに低学年は、親が「一緒にやろう!」と言うと素直に取り組むことが多い
小学校低学年のお子さんは、まだまだ親の存在が学習への影響を強く持っています。
「やりなさい」ではなく「一緒にやってみよう」というスタンスで関わるだけで、子どもの反応は大きく変わってきます。
すららの授業はアニメーションや会話形式で進むので、親子で見ていても楽しく、「ここわかる?」「面白いね」などの会話が自然に生まれる構成になっています。
親が前向きに取り組んでいる姿勢を見せることで、子どもも「勉強=ポジティブなこと」と認識してくれるようになります。
学びを家庭のコミュニケーションの一部にしていくことが、学習習慣の土台をつくる第一歩です。
使い方4・苦手克服から入るのがおすすめ/ 好きな科目ばかりやると偏るから、すららのAI診断で弱点を把握して、そこから攻略する
好きな教科だけに偏りがちなのは、小学生の学習でよくあるパターン。
でも、バランスよく学ぶには、まず苦手を克服することが大切です。
すららのAI診断機能を活用すると、どこに弱点があるかを具体的に可視化してくれます。
そのデータをもとに、「この単元からやってみよう」と一緒に計画を立ててあげると、子どもも目的を持って取り組みやすくなります。
最初は苦手意識があっても、「分かった!」という成功体験が積み重なることで、自信へと変わっていきます。
不得意な部分から着実に取り組むことが、学力の底上げにつながっていくはずです。
【中学生】すららの効果的な使い方について紹介します
中学生になると、定期テストや内申点を意識した学習が重要になってきます。
すららは、教科書の内容に沿って単元ごとに進められ、テスト範囲に合わせた計画的な学習がしやすい設計になっています。
また、部活や習い事で忙しい中学生にとって、「短時間でも成果が出やすい」「AIで弱点が明確にわかる」点も大きなメリットです。
毎日のスキマ時間を活用して、テスト対策・苦手克服・先取り学習など、それぞれの目的に応じた使い方をしていくことで、塾に通わなくても高い効果が期待できます。
ここでは、そんな中学生向けの具体的な活用法をご紹介していきます。
使い方1・「定期テスト対策」に直結させる/単元ごとにまとめテストがあるから、テスト範囲を逆算して、今どこをやるべきか計画を立てる
すららには、単元ごとに「まとめテスト」が用意されていて、テスト前の実力チェックや仕上げにぴったりです。
学校の定期テスト範囲が発表されたら、その範囲を逆算して、どこからどれくらいのペースで進めればよいかを計画していくと、効率よく対策が進みます。
AIがつまずきやすいポイントを自動で提示してくれるので、苦手な単元から優先的に取り組むのも効果的です。
計画的に進められると、「まだ何もしていない…」という焦りがなくなり、自信を持ってテストに臨むことができます。
学習の進捗が画面上で見えることで、やる気も維持しやすくなりますよ。
使い方2・部活後の「夜学習」を習慣に/寝る前の「タブレット学習ルーティン」を決めると、ペースが乱れない
中学生は部活や習い事で忙しい時期。
帰宅後はつい「今日は疲れたから…」と後回しになりがちですが、だからこそ“夜のルーティン化”がカギになります。
たとえば、夕食後やお風呂のあとに30分だけすららに取り組む時間を設けて、「寝る前の習慣」として固定してしまうと、ペースが乱れにくくなります。
テレビやスマホよりも先に「ちょっとだけやる」という意識を持てると、勉強が負担に感じにくくなるんです。
すららの内容は1回20~30分ほどで完結するので、夜学習にもぴったり。
集中力が切れないうちに取り組めるボリュームなので、毎日の積み重ねにちょうどいいんですよ。
使い方3・「すららコーチ」をフル活用/学習計画のアドバイスやつまずきのサポートをしてくれる
すららの大きな特徴のひとつが、学習をサポートしてくれる「すららコーチ」の存在です。
中学生になると、自分で計画を立てる力が必要になってきますが、なかなかうまく進められないこともありますよね。
そんな時に、コーチが進捗状況を確認して「この単元を優先しましょう」「苦手な部分を復習してから次に進みましょう」と具体的なアドバイスをくれることで、迷いなく学習を進めることができます。
また、つまずいている部分を丁寧に見つけてくれるので、必要以上に悩まずに軌道修正ができるのも心強いポイントです。
自分一人では気づけないことも、コーチのサポートがあるとぐっと学びやすくなりますよ。
使い方4・「復習と予習」をバランスよく/英語や数学の文法・公式の理解は予習でやると授業が楽しくなる
すららの教材は、無学年式で学べるため「今の自分に必要なレベル」から始めることができます。
中学生にとっては、予習と復習のバランスがとても大切。
たとえば、英語の文法や数学の公式は、すららで予習しておくと、学校の授業が“確認”になり、自信を持って参加できるようになります。
また、授業を聞いて「あれ?」と感じたときには、家ですららで復習して解決することもできるんです。
テスト前には復習中心、授業内容が難しくなる時期には予習中心と、柔軟に使い分けられるのがすららの強み。
授業に置いていかれないための“お守り”として、うまく取り入れていきたいですね。
【高校生】すららの効果的な使い方について紹介します
高校生になると、勉強の難易度も上がり、進路を意識した学習が必要になってきます。
学校の授業についていけなかったり、模試の結果に焦ったりすることもありますよね。
そんなとき、すららは基礎をしっかり固めたい人、マイペースに学びたい人にとって大きな味方になります。
教科書に準拠した内容で、苦手な単元を基礎から復習できるのはもちろん、得意な科目を先取りすることも可能です。
タブレット一台で、時間や場所に縛られずに学べるのも高校生にはうれしいポイント。
ここでは、高校生がすららを活用する上での効果的な使い方を、4つの観点から紹介していきます。
使い方1・「苦手克服」×「得意分野の強化」を並行する/つまずいてるところは基礎から復習し、得意分野は応用問題に挑戦する
高校の学習は、ひとつのつまずきがその後の理解にも大きく影響することがあります。
すららは、どの単元まで戻っても学べる無学年式だからこそ、苦手部分は徹底的に基礎からやり直すことができます。
たとえば英語の文法や数学の計算に不安があるときには、必要なレベルまで一度戻って復習し、そのうえで応用問題に取り組むと理解度が一気に高まります。
一方で、得意科目については発展的なユニットにも挑戦できるので、「苦手克服」と「得意の強化」を並行して進めることができるんです。
このバランス感覚が、成績アップや入試対策の基盤になっていきますよ。
使い方2・学校の授業が合わない場合は、すららで自分に合うペースで進める
高校の授業は進度が早く、「あれ?まだ理解しきれてないのに…」と置いていかれることも少なくありません。
そんな時に無理についていこうとすると、ますます分からなくなってしまうことも。
すららなら、授業に合わせる必要がなく、自分のペースでゆっくり確実に進めることができます。
「分からないところに戻る」「得意なところは先に進む」など、自分に最適な学びができるのが強みです。
学校の授業に合わなくても、家庭学習ですららを取り入れることで、学びの軸を自分に取り戻すことができます。
焦らず、でも確実に前に進みたい高校生にはぴったりの教材なんです。
使い方3・模試や共通テスト対策に連動/すららは基礎力の定着にはかなり強い
高校生にとって模試や共通テストは、自分の実力を知る大切な機会ですよね。
特に共通テストでは「基礎力を問う問題」が多く出題されるため、いかに基本をおろそかにせず定着させるかがカギになります。
すららは、基礎の解説が丁寧で、理解→練習→確認の流れがしっかりしているため、基礎固めには非常に強い教材です。
模試の結果を見て「この単元が苦手かも」と思ったら、すららで該当単元を復習すれば、効率よく穴を埋めることができます。
難問に挑む前に、まずは基礎をしっかり固めておくこと。
それを実現できるのが、すららの良さなんです。
使い方4・学習時間を「見える化」する/学習時間や達成度がグラフで表示される
高校生になると、自分の勉強を“管理する力”も大切になってきます。
すららには、学習時間や進捗、達成度などをグラフで見える化してくれる機能があります。
これによって、「どれくらい勉強したか」「どこがまだ弱いか」が一目で分かるようになり、自分で学習の調整がしやすくなります。
「今日は30分頑張れた」「先週より多くできた」といった小さな達成感が積み重なることで、やる気の維持にもつながるんです。
目に見える成長は、自己管理能力の向上にもつながるので、大学進学を見据えた学習習慣づくりにもすららは役立ちます。
【不登校】すららの効果的な使い方について紹介します
不登校のお子さんにとって、学校のような「集団」や「対面」での学習はプレッシャーになることが多く、勉強からも距離ができてしまうケースが少なくありません。
そんなとき、すららは家庭内で安心して学習ができる環境をつくるための大きな味方になってくれます。
自分のペースで、誰にも見られず、焦らず進められるのがすららの良いところ。
さらに、親子で一緒にスケジュールを立てたり、キャラクターのやり取りを楽しんだりすることで、「勉強=苦しいもの」というイメージを少しずつやわらげていくことができます。
学校復帰を目指す前の“リハビリ学習”としても非常に有効です。
使い方1・「生活リズム作り」に役立てる/朝起きる→学習→休憩…の「ミニ時間割」を作って生活リズムを整えられる
不登校の期間が続くと、どうしても生活リズムが崩れがちになりますよね。
夜型になったり、起きる時間が毎日バラバラだったり…。
そんな時に、すららを活用して“朝の学習”を取り入れると、自然とリズムが整いやすくなります。
「朝起きたらまず30分だけすららをやる」といった“ミニ時間割”を家庭内で決めることで、1日のスタートに目的が生まれます。
また、すららのユニットは短く完結するので、集中が続かなくても無理なく取り組めるのが嬉しいところ。
生活リズムが安定してくると、気持ちも落ち着きやすくなり、日常の安心感も少しずつ戻ってきますよ。
使い方2・「一人でも安心してできる環境」を整える/自分のペースで、周りを気にせず学べるのがすららの強み
学校での集団行動や他人の目がストレスになりやすい不登校のお子さんにとって、「一人で落ち着いて学べる環境」はとても重要です。
すららは、完全非対面で、アニメーションキャラクターが優しくナビゲートしてくれるスタイルなので、プレッシャーなく学習を進めることができます。
また、自分の理解度に合わせて進められる無学年方式なので、「できなかったらどうしよう」という不安もなくなります。
周囲と比べられない安心感の中で、自分のペースを大切にしながら学ぶことができるため、「やってみようかな」と思えるきっかけづくりとしても最適です。
使い方3・「成功体験」を増やして自信を回復/すららの「ほめ機能」を活用する
不登校の経験がある子は、「自分はできない」「どうせダメだ」といった自己否定感を抱きやすいことがありますよね。
すららは、そんな子どもたちの自己肯定感を取り戻すサポートをしてくれる教材です。
なかでも注目したいのが、“ほめ機能”。
正解したときやユニットをクリアしたときに、キャラクターがやさしく褒めてくれることで、「できた!」という実感が積み重なります。
この小さな成功体験の積み重ねが、「自分にもできるかもしれない」という前向きな気持ちにつながり、少しずつ自信を取り戻すきっかけになっていくんです。
無理に頑張らせなくても、「楽しかったからまたやろう」と思える工夫が詰まっているのが、すららのやさしさです。
使い方4・コーチングの活用で「孤立感」を減らす/すららコーチに相談すると、親とは違う「第三者の声」がもらえるので、気持ちの負担が和らぐ
不登校のお子さんは、自宅にいても孤独を感じることが多く、「誰にも相談できない」「話すのが怖い」と心を閉ざしてしまうこともあります。
そんな時に、すららの「すららコーチ」は大きな支えになってくれます。
親とは違う第三者として、やさしく声をかけてくれる存在がいるだけで、子どもの気持ちは少しずつほぐれていくもの。
学習面だけでなく、「今日は何をしたか」「どこが分かりにくかったか」などの会話ができるようになると、「自分は一人じゃないんだ」と感じられるようになります。
無理に学校へ戻すのではなく、「今できることを一緒に進めよう」という姿勢で寄り添ってくれるのが、すららコーチの魅力です。
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららを実際に利用したユーザーの口コミ・評判を紹介します
良い口コミ1・うちの子は、元々タブレットが好きで、ゲーム感覚で学べるところがハマったみたいです。アニメのキャラが優しく教えてくれるので、塾に行くよりも緊張しないし、自分のペースでできるのが良いみたい
良い口コミ2・ADHD気味で集中力が長続きしない子でも、すららはアニメーションやイラストで説明してくれるので理解しやすいです
良い口コミ3・学校に通えない期間が長く、勉強にブランクがありましたが、すららなら自分のレベルに合わせて無理なく進められました。先生の顔を見ずに自分だけのペースで学べるので、安心感があります
良い口コミ4・塾に通う時間が取れなかったけど、すららは家でスキマ時間にできるから便利!部活が忙しくても、夜に少しずつ進めていけるし、テスト対策にも使えるのがいい
良い口コミ5・発達に凸凹があって、書くことが苦手な子ですが、すららはタブレット操作で進められるので、嫌がらずに学習ができています
悪い口コミ1・タブレットで勝手に学んでくれると思っていたけど、低学年の子は一人で進めるのが難しいこともあり、結局そばで見守ることに…。もう少し親が楽できる設計だったらよかったかな
悪い口コミ2・初めは楽しく続けられていたのですが、不登校の子だと一度やる気が下がると放置してしまう…。サポートメールや先生からのアドバイスは来るけど、やっぱり一人だと限界を感じることもあります
悪い口コミ3・高校生用のコースを受講していますが、基礎に時間をかけすぎる印象です。進学校に通っていると、物足りなさを感じるかもしれません
悪い口コミ4・アニメーションで楽しく学べるのはいいけれど、うちの子は飽きるのも早くて…。もう少し、変化に富んだコンテンツがあると良いですね
悪い口コミ5・通塾よりは安いですが、長期間利用を考えるとそれなりに負担感があります。特に兄弟で同時に使う場合は、一人ずつの契約が必要なので、コストはやっぱりかさみます
【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの会社概要を詳しく紹介します
子どもの学習にタブレット教材を取り入れようと思ったとき、まずチェックしたいのが「その教材を作っている会社が信頼できるかどうか」ですよね。
すららは、見た目の親しみやすさから子どもに好評な一方で、実際の運営会社がどうなのか気になる保護者の方も多いと思います。
すららを提供している「株式会社すららネット」は、学校・塾・家庭向けのオンライン教材を開発・提供する教育系の専門企業。
東証グロース市場に上場していることからも、社会的な信頼性の高さがうかがえます。
今回は、この会社がどんな企業なのか、導入前に知っておきたい情報をわかりやすくお届けします。
| 運営会社 | 株式会社すららネット |
| 創業 | 2008(平成20)年8月29日 |
| 本社住所 | 〒101-0047
東京都千代田区内神田1-14-10 PMO内神田7階 |
| 従業員数 | 正社員88人、契約社員5人 |
| 資本金 | 298,370千円 |
| 代表取締役 | 湯野川 孝彦 |
| すらら公式サイト | https://surala.co.jp/ |
| すららの講座一覧 | ・3教科(国・数・英)コース
・4教科(国・数・理・社)コース ・5教科(国・数・理・社)コース |
参照:会社概要(すらら公式サイト)
【すらら】はうざい!?についてのよくある質問と回答
すららについて検索していると、「うざい」「最悪」といったネガティブなワードが出てくることがありますよね。
これから利用を検討している保護者の方にとっては、「本当に大丈夫かな?」と不安になる瞬間かもしれません。
でも、実際の利用者の声を見ていくと、こうした印象は必ずしも教材そのものに対するものではなく、“使い方”や“相性”に起因しているケースが多いんです。
この記事では、「すららってどうなの?」という疑問に答える形で、よくある質問を取り上げ、それぞれわかりやすく解説しています。
関連ページもあわせてチェックすることで、より具体的な情報を得られるはずです。
ぜひ不安解消の一助になれば嬉しいです。
すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?
「すらら うざい」といった検索ワードが表示されると、少し身構えてしまいますよね。
でも、これには理由があります。
実際にそう感じた方の声を見てみると、「親が見張ってくるのが嫌だった」「毎日やらされてる感があった」など、教材そのものというより“学習環境”や“保護者との関わり方”に対するストレスが要因になっているケースが多いようです。
また、すららは自分のペースで進める無学年式の教材なので、「サボれる」と感じてしまう子どもにとっては逆にやりづらさを感じることもあるかもしれません。
とはいえ、実際の満足度は高く、特に発達特性があるお子さんや不登校の子には合いやすい教材として評価されています。
関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較
すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください
すららには発達障害や学習障害に対応した「特別支援コース」があり、対象となる方には通常よりも安い料金で提供されるプランがあります。
たとえば、療育手帳を持っているお子さんや、医師から診断を受けている場合は「特別料金プラン」の申請が可能で、入会金の割引や月額費用の軽減などの優遇が受けられることがあります。
このプランを利用するには、必要書類の提出が必要になりますが、申請自体はそこまで難しくありません。
すららネットとしても、発達特性のあるお子さんが学びやすい環境を整えることを大切にしているため、サポート体制も充実しています。
関連ページ:すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?
すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?
すららは、学校に通えない状況にあるお子さんでも「出席扱い」として認められるケースがある家庭用教材です。
これは、文部科学省が定める「ICTを活用した学習支援の出席扱い制度」に準拠した教材であるため、学校や自治体の承認が得られれば、在宅学習でも正式な出席日数としてカウントされる仕組みです。
ただし、すべての学校で一律に認められるわけではないため、事前に学校や教育委員会への相談・申請が必要になります。
申請にあたっては、学習の進捗状況や教材の利用記録の提出が求められることもあるので、あらかじめ準備しておくと安心です。
関連ページ:すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて
すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください
すららでは、期間限定の「キャンペーンコード」が配布されることがあり、これを使うと入会金が無料になったり、特別な特典がつくことがあります。
コードの入手方法としては、公式サイトやメルマガ、口コミサイト経由などがあり、時期によってはSNSなどでシェアされていることもあります。
使い方はシンプルで、入会手続きの際に「キャンペーンコード入力欄」にコードを記入するだけで適用されます。
入力ミスや期限切れには注意が必要ですが、わずか数秒でお得になるなら活用しない手はありません。
申し込みを検討している方は、事前に有効なコードがあるかチェックしてみるのがおすすめです。
関連ページ:すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について
すららの退会方法について教えてください
すららの退会は、Webからではできず「電話」での手続きが必要です。
これは少し面倒に感じるかもしれませんが、オペレーターが丁寧に対応してくれるため、手続き自体はスムーズです。
まず「解約」と「退会」は異なり、「解約」は毎月の利用料の支払いを停止し利用をストップするもの、「退会」は会員情報や学習データも完全に削除する手続きになります。
多くの方は、まず「解約」だけをして学習記録を残しておくケースが多いようです。
再開する可能性があるなら、退会まではせずにおくのがおすすめです。
電話の際に、どちらを希望するかきちんと伝えるようにしましょう。
関連ページ:すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?
すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?
基本的に、すららでは「入会金」と「毎月の受講料」以外に大きな費用はかかりません。
追加教材の購入や、専用端末なども不要で、自宅にあるパソコンやタブレット、ネット環境さえあればすぐに始めることができます。
ただし、特別支援対応コース(発達障害支援など)を利用する場合は、追加で月額1,100円程度の費用が発生することがあります。
また、兄弟など複数人で利用する場合には、それぞれにアカウントが必要となるため、人数分の受講料がかかります。
キャンペーンのタイミングで入会金無料などの特典もありますので、最新情報を確認しながら申し込みを検討するのが安心ですね。
1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?
すららは「一人ひとりに最適な学び」を提供する無学年式の教材であるため、基本的には「1人=1アカウント」となっています。
兄弟で同じアカウントを共有して使うことは推奨されておらず、進捗状況が混ざったり、AIによる弱点分析が正確にできなくなってしまいます。
ただし、兄弟で別アカウントを契約する場合には「兄弟割引制度」が利用できることがあります。
割引の内容や条件はその時期によって異なるため、申し込み時に問い合わせてみると安心です。
それぞれの学年や理解度に合わせて無理なく進められるのが、すららの強みです。
すららの小学生コースには英語はありますか?
はい、すららの小学生コースには英語も含まれています。
英語学習が小学校でも必修化される中、すららでは「楽しく学べる英語」をコンセプトに、基礎からしっかり学べるカリキュラムが用意されています。
英単語の読み書きはもちろん、ネイティブの発音が聞ける音声教材、会話文のリスニングなど、五感を使った学習ができるのが特徴です。
キャラクターが丁寧にナビゲートしてくれるので、英語に苦手意識のあるお子さんでも無理なく取り組めます。
また、学年に関係なく自分のレベルから始められる無学年式なので、英語が得意な子は先取り学習も可能です。
すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?
すららには「すららコーチ」という学習サポート担当がついており、日々の学習を丁寧に見守ってくれる仕組みがあります。
コーチは、お子さんの理解度や性格、家庭の状況に応じて学習計画を提案してくれたり、「この単元が苦手そうです」といったフィードバックをくれたりします。
さらに、定期的に保護者にも連絡をくれるので、親がすべてを管理しなくても安心して任せることができます。
特に発達障害や不登校の支援を希望する場合には、その特性を理解したうえで、無理のない進め方を一緒に考えてくれるので、子どもも「ひとりじゃない」と感じられるようになります。
参照:よくある質問(すらら公式サイト)
【すらら】はうざい!?他の家庭用タブレット教材との違い比較しました
毎月の学習費用って、意外と積み重なるものですよね。
タブレット教材も月額制のものが多く、「ちゃんと効果があるのか」「他と比べて高くないか」が気になる方も多いと思います。
すららは月額8,000円台から始められる教材ですが、「少し高い?」と感じる人もいるかもしれません。
けれど、その料金の中にどんなサポートや機能が含まれているかまで見ると、また違った印象になるかもしれません。
この記事では、すららと他の主要な家庭用タブレット教材を、料金・内容・サポートのバランスで比べてみました。
コスパを重視しつつ、子どもに合った教材選びをしたい方にぴったりの内容です。
| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |
| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |
| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |
| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |
| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |
| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |
| ヨミサマ。
|
16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |
| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |
【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は本当?タブレット教材の口コミ比較まとめ
すららは「うざい」や「最悪」などの噂が出回っている一方で、実際に使ってみると「子どもが楽しそうに学習している」「他の教材より合っていた」という声も多く、評価は本当にさまざまです。
無学年式・対話型・AI分析など、特徴的な学習スタイルは他の教材にはない魅力でもあり、合う子にとってはまさに救世主のような存在になることも。
料金についても、一見高く感じるかもしれませんが、サポート体制や機能を考えると納得できるケースが多いです。
まずは体験してみて、「合うかどうか」を自分の目で確かめることが何より大切。
世の中の評判に惑わされすぎず、我が子にとっての“ベスト”を見つけてくださいね。